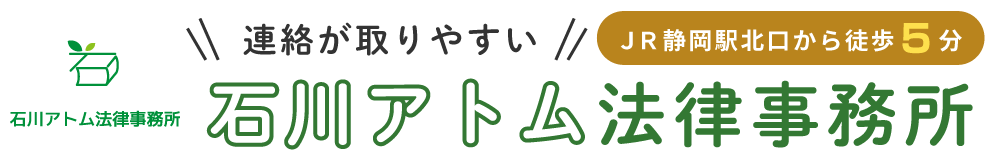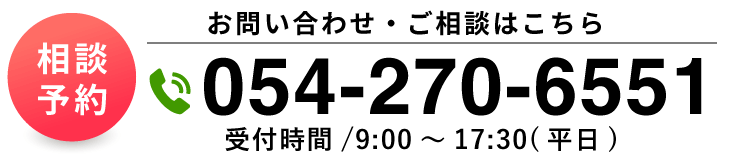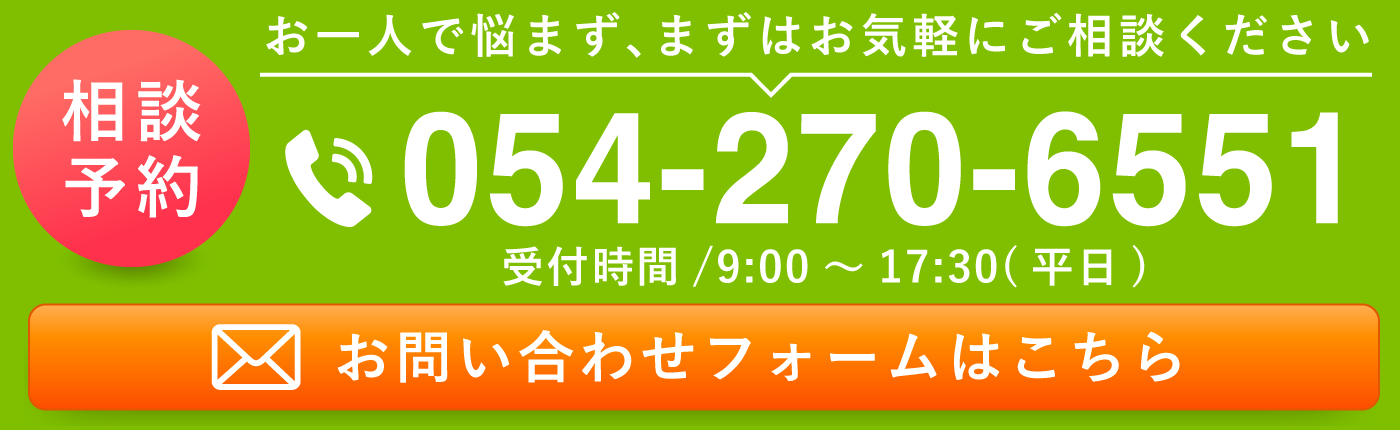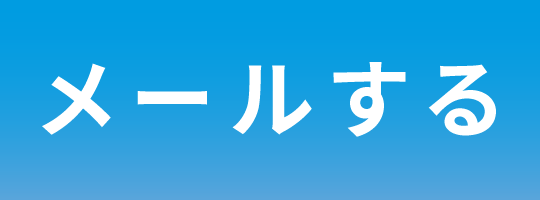Author Archive
弁護士ドラマでよく見る刑事事件~被疑者国選2
あくまで当事務所の「推し」は、自己破産、交通事故、顧問業務(顧問弁護士)なのですが
皆さん、こんにちは。弁護士の石川アトムです。
早いもので、2024年も、もう1月経ってしまいますね。
今回も前回の記事に引き続き、弁護士が取り扱う刑事事件についてお話をしたいと思います。
あくまで弁護士石川の「推し」は、自己破産事件、交通事故事件、顧問業務(顧問弁護士業務)なのですが、当法律事務所の新しい事務員さんに、弁護士の業務内容を理解してもらうという目的もあり、刑事事件について書いています(実際、昨日、事務員さんが当ブログを読んでいました!)。
今回は、「被疑者国選」を受任した弁護士の活動内容からお話ししたいと思います。
弁護人としての活動~被害者へのお詫び
弁護士が被疑者国選事件を受任すると、担当となる被疑者が勾留されている期間中、弁護人として活動をすることになります(「被疑者」に関するご説明は、こちらの記事をご覧ください)。
国選、私選に限らず言えることですが、弁護人が行う業務として、分かりやすいものとしては、被害者へのお詫びや被害弁償が挙げられます。
たとえば、Aさんが万引きをしてお店の商品を盗んでしまったという事件を担当するとします。
通常、弁護士は、警察や検察を通じて、お店の連絡先、担当者の名前を教えてもらいます。
そして、弁護士は、お店に電話を掛け、まず謝罪をし、その後、Aさんが盗んでしまったものの金額を弁償させていただきたい旨を伝えます。
ただし、Aさんやその親族、友人らが、弁償できるだけのお金を持っていない場合には、そもそも弁償のお話をすること自体ができません。
被害弁償の提案を受けたお店の対応は様々です。
多数の店舗を出店している大きなスーパーなどでは、会社の統一的な方針として、「万引きは絶対許さない。だから被害弁償には一切応じない。」ということがあります。
そうなると、弁護士としては、電話でお詫びをするだけで、被害店への対応は終了となってしまうことが多いでしょう。
他方で、被害弁償に応じていただけるお店もあります。
電話での謝罪の際に、被害弁償に応じていただけるということになれば、お店に伺う日時を調整します。
そして、弁護士が、Aさんや、その親族等の関係者から、Aさんが万引きした商品に相当するお金を預かり、あるいは、お金を用意してくれる親族等を伴って、被害店舗に赴きます。
そして、被害店舗で万引きに関して、改めてお詫びをするとともに、被害弁償をさせていただきます。
電話でのお詫びの際、電話口での被害者側の雰囲気によっては、被害弁償によりAさんを許していただけるかどうかの意向を確認します。
許していただけるということであれば、その内容を含んだ示談書を作成して、被害弁償の当日に持参します。
電話で示談の話をすることがはばかられるような雰囲気の場合、私の場合、まずは、被害弁償をさせていただきます。
そして、弁償金をお受け取りいただいた後、その場の雰囲気を見て、示談の話をすることがあります。
このような場合には、事前に、最終的に示談まではできないかもしれないけれど、示談の成立前に弁償金を支払うことについて、被疑者や関係者から承諾を得ておきます。
以上は、万引きに関するケースですが、事件によっては、交通事故の被害者のご自宅へお詫びに伺う、下着泥棒の被害者のご自宅にお詫びに伺う、ということもあり得ます。
このように、被害者がいる犯罪の場合、被害者へのお詫びと被害弁償は、弁護人として行う主な業務内容の一つです。
弁護人としての活動~取調べに対するアドバイス等
弁護人としての活動のうち、大きなものの一つが、警察署や拘置所で捕まっている人と面会をし、必要なアドバイスをするというものです。
私が弁護人として、警察署などで被疑者と最初に面会する際、誰に対しても、毎回必ず同じことを伺います。
1つ目は、捕まった理由とされている事実(その人がやったと疑いを掛けられている事実=「被疑事実」といいます)について、間違いないかどうか、ということです。
特に、被疑事実に誤りがあるという場合(いわゆる「否認事件」の場合)には、裁判において当該事実の存否を争うことが予想されます。
被疑者は、警察署や検察庁の取調べの中で、被疑者が供述した内容をまとめた書類(「供述調書」といいます)に署名押印することを求められます。
被疑者が供述調書に署名押印すると、裁判になったときにその内容をひっくり返すことは極めて困難です。
また、近時は、被疑者に対する取調べの内容が録音録画されていることもあります。
そのため、被疑者が、警察や検察に対して何を話すのか、何を話さないのか、ということは、後の裁判の場面で大きな意味を持ってきます。
被疑者から、被疑事実について、どこがどのように間違っているのかを確認し、間違っている部分について、警察や検察に話をするのかしないのかという方針を決め、必要なアドバイスをすることは弁護人の重要な職務の一つです。
事件によっては、弁護人となった後、定期的に警察署に赴き、被疑者と面会をして、捜査機関への対応について打合せをする必要があります。
弁護人としての活動~最終的な処分の見通し
私が、初回の面会で被疑者に尋ねる2つ目の内容は、これまで警察のお世話になったことがあるかどうかということです。
これまで警察のお世話になったことがあるかどうかによって、その事件が不起訴(前科が付かない処分)で終わるのか、罰金刑を前提とした書類だけの裁判(「略式裁判」「略式請求」といいます)で終わるのか、ニュースで見るような裁判所での正式裁判(「公判請求」ともいいます)まで行ってしまうのかが、ある程度予測できます。
特に、以前にも刑事裁判を受けたことがあり、前科がある人については、今回逮捕された事件についても厳しい処分が予想されます。
今後の刑事手続がどのようなスケジュールで進むのか、いつ警察署から出られそうなのか(あるいは、そのまま刑務所に入ることになりそうなのか)は、前科前歴の有無に大きく左右されます。
そのため私は、初回の面会で、必ず、「失礼な質問で申し訳ありませんが、これまで警察のお世話になったことはありますか。」と尋ねることにしています。
静岡を拠点に活動する弁護士の石川アトムと申します。静岡市に育ち、大学時代に祖母が交通事故に遭ったことをきっかけに、人の人生の大切な一歩を支えたい気持ちが芽生えました。東北大学法学部や京都大学法科大学院で学び、地元で弁護士として働きたい想いを胸に、2022年に独立開業し、石川アトム法律事務所を立ち上げました。事件の進行状況や今後の見通しをこまめに伝えるよう心がけ、ご相談者さまの安心につながればと思っています。趣味は英会話。
弁護士ドラマでよく見る刑事事件~被疑者国選1
「容疑者」は法律用語ではありません
皆さん、こんにちは。弁護士の石川アトムです。
今回も前回の記事に引き続き、刑事事件について、弁護士ってこういう仕事をしているんだよ、という観点からお話をしたいと思います。
前回の記事では、主として、私選弁護人と国選弁護人についてお話をしました。
今回の記事では、国選弁護人に関連する「被疑者国選」という制度についてお話をします。
なお、今回の記事は、基本的に、弁護士石川が所属する静岡県弁護士会の静岡支部での取扱いを前提としたものです。
他支部、他県での取扱いは異なる場合がありますので、ご了承ください。
さて、「被疑者」国選という制度を紹介する前に、まず、「被疑者」とは何かということについてお話します。
「被疑者」というのは、警察や検察から、何か犯罪行為を行ったのではないかということで、捜査の対象となっている人のことを言います。
ただし、捜査の対象となっている人が刑事裁判にかけられると、その人は「被告人」と呼ばれることになります。
警察や検察で捜査の対象となっていて、刑事裁判になる前の人が「被疑者」、刑事裁判に掛けられた人が「被告人」ということです。
テレビのニュースなどでは、よく「容疑者」という言葉が使われますが、「容疑者」は、いわゆる法律用語ではありません。
私が聞いたところによると、マスコミが、「被疑者」と「被害者」の音が似ていて混同しやすいため、「容疑者」と「被害者」という呼び方をするようになったとかならなかったとか・・・。
被疑者国選って何ですか
警察や検察で捜査の対象となっていて、刑事裁判になっていない人のことを「被疑者」と呼びます。
そうしますと、「被疑者国選」というのは、警察や検察から捜査の対象とされている人に付く、国が選んだ弁護人ということになりそうです。
しかし、捜査の対象となっている人に「被疑者国選」が選ばれるためには、もう少し別の要件も必要です。
その要件の一つが、裁判所によって「勾留」の裁判を受けていることです。
「勾留」というのは、警察署の留置場や拘置所に捕まえたままにしておく、という裁判所の決定のことです。
裁判に掛けられる前の「勾留」、つまり、被疑者段階での「勾留」の期間は、最長10日間(1回に限り10日間の延長あり)です。
たとえば、Aさんが、万引きをして逮捕されたとします。
検察官は、Aさんについて、逮捕のときから最長でも72時間以内に「勾留」の請求をするかどうかを決めなければいけません。
「勾留」の請求が裁判所によって認められると、「勾留」の決定があった日を含め、最長10日間
(1回に限り10日間の延長あり)捕まったままの状態になります。
国選弁護人を選任することができるのは、この「勾留」が認められた時点からです。
逆に言うと、私選弁護人を選任しない限り、「勾留」決定がされる前には、弁護人は付かないということです。
被疑者国選が選ばれるまでの流れ
本項目については、弁護士石川が実際の業務内容を見たわけではないため、石川の想像が入るところで、ここに書かれている内容が全て正しいかどうかは保証できません。
先ほどお話したように、検察官が「勾留」の請求を行い、裁判所が「勾留」の決定を出すと(裁判所が「勾留」の決定を出さないこともあり、その場合、被疑者はその時点で釈放されます)、「勾留」されてしまった「被疑者」は、その他の一定の要件をクリアしたうえで、国選弁護人(被疑者国選)を付けることができます。
国選弁護人の希望があると、おそらく裁判所から法テラスという機関に、被疑者の氏名、生年月日、行ったと疑われている犯罪の内容等とともに、国選弁護人の選任を希望しているという連絡が行きます。
そのような連絡を受けた法テラスは、その日に、国選弁護事件を担当することが予定されている弁護士に連絡を取り、その弁護士が国選弁護事件を受けられるかどうかの確認をします。
「国選弁護事件を担当することが予定されている弁護士」が誰なのかということについて、静岡県弁護士会の静岡支部では、1日ごとに予め担当者が定められています。
1月21日はX弁護士、1月22日はY弁護士、1月23日はZ弁護士といった具合です。
私の記憶が正しければ、少なくとも静岡支部では、法テラスから連絡を受けた弁護士は、当該被疑者との利益相反などがない限り、基本的に、被疑者国選を受けられるかという打診を受けた事件については受任しなければいけないというルールになっていたはずです。
国選弁護事件の場合、被疑者側に弁護人を選ぶ権利がないことは、前回の記事で申し上げましたが、事件を受ける弁護士の側でも、基本的に拒否権は無かったはずです。
事件の配点を受ける弁護士の側でも(少なくとも静岡では)、性犯罪の事件はやりたくないから受けないとか、遠い警察署は大変だから受けないとか、そういったことは許されなかったはずです。
静岡を拠点に活動する弁護士の石川アトムと申します。静岡市に育ち、大学時代に祖母が交通事故に遭ったことをきっかけに、人の人生の大切な一歩を支えたい気持ちが芽生えました。東北大学法学部や京都大学法科大学院で学び、地元で弁護士として働きたい想いを胸に、2022年に独立開業し、石川アトム法律事務所を立ち上げました。事件の進行状況や今後の見通しをこまめに伝えるよう心がけ、ご相談者さまの安心につながればと思っています。趣味は英会話。
弁護士ドラマでよく見る刑事事件~弁護士が実際に行う仕事の中身
刑事事件は意外と少ない
新年明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
さて、早速ですが、今回から数回にわたり、刑事弁護、刑事裁判についてお話ししたいと思います。
弁護士を主人公としたテレビドラマは枚挙に暇がありませんが、その多くは、刑事事件を題材としたものです。
私の中での弁護士を主人公としたテレビドラマのイメージは、
弁護士が事件現場にたびたび訪れ、自力で目撃者を探し出し、最後には真犯人が暴かれる
みたいな感じですが、現実に刑事弁護をやっている弁護士からすると、あり得ないストーリーです。
そもそも当事務所での刑事事件の取扱いは非常に少ないです。
全案件数に占める割合は、平均で言えば5%を切ると思います。
静岡でも、刑事弁護が得意という看板を出している法律事務所、弁護士もいらっしゃいますが、極めて少数派だと思います。
なお、当事務所の「売り」は、自己破産、交通事故、顧問弁護士(顧問業務)であり、刑事事件ではありません。
それでは、なぜこれからのブログで、刑事事件について書くのかと言いますと、当事務所に新しく入所された2名の事務員さんへの説明を兼ねているからです。
2名の事務員さんは、ともに法律事務所での職務経験がありません。
そこで、ブログで弁護士の仕事の内容を書いておくから読んでおいてね、ということにしました。
そのため、普段はそれほど取扱いのない、けれども、何となく弁護士のイメージとして馴染みやすい刑事事件について、これから何回かのブログで書いていくことにしたのです。
国選弁護人と私選弁護人
まずは、この2つのワードの意味からご説明いたしましょう。
2つのワードの違いは、一目瞭然、「国」と「私」です。
国で選んで付けた弁護士が国選弁護人、自分で弁護士を選んで付けた場合が私選弁護人というわけです。
私選弁護人の場合、どの弁護士を選ぶかは自由ですが、その弁護士との契約にしたがって、弁護士費用を支払う必要があります。
国選弁護人の場合、弁護士を選ぶことはできません。
静岡(静岡支部)において、どの弁護士が国選弁護人として付くのかということについては、予め定められた名簿の順番に従って、機械的に割り振られていきます。
1月1日はX弁護士、1月2日はY弁護士、1月3日はZ弁護士といった具合です。
国選弁護人が付いた事件で弁護士費用を支払う必要があるかどうかはケースバイケースです。
テレビドラマで見るような、公開の法廷で裁判を受けるケースでは、懲役○○年などという判決と同時に、国選弁護人の費用をその人に負担させるかどうかが裁判官によって決められます。
通常は、その人の財産や収入の状態を見て、国選弁護人の費用を負担させるかどうかが決められます。
国選弁護人と私選弁護人の違い
特に、これまで刑事事件に縁が無かった人が逮捕された場合などに気にすることが多いと思うのですが、国選弁護人と私選弁護人で、できる内容や権限に違いはあるのでしょうか。
結論から言えば、ありません。
刑事事件、刑事裁判に関して、私選弁護人でなければ行うことができない手続というものはありません。
それでは、国選弁護人と私選弁護人が同じ権限を持っているとして、やってくれる内容に違いはあるのでしょうか。
結論としては、基本的には無い、と思います。
「基本的には」というと歯切れが悪いのですが、まず、全般的な話、包括的な話として、私選だからしっかりやるとか、国選だからいい加減にやってもいいと思っているとか、そのような弁護士は、少なくとも国選登録をしている静岡(静岡支部)の弁護士にはいないと思います。
国選弁護人は「保釈」(また別の記事でご説明します)の手続をしてくれないから、私選弁護人を付けた方がいいとか、そういったことはありません。都市伝説です。
逮捕されてしまった人、裁判に掛けられた人の弁護や、留置場、拘置所から出るために必要と考えられる手続については、国選であっても、私選であっても、弁護人がやる内容に変わりは無いと思います。
ただし、先ほども申し上げたとおり、国選でも、私選でも、「基本的には」同じようにやるのだと思いますが、「弁護に必要な事項」や「留置場、拘置所から出るために必要と考えられる手続」以外の事項については、国選と私選で違いが出ることはあるのだろうと思います。
たとえば、これまで全く警察のお世話になったことがなかった人が、覚せい剤を使ってしまい、逮捕されてしまったという事件を想定します。
本人が覚せい剤を自発的に使ったことを認めていて、尿検査で覚せい剤が検出されているような場合、このような事件では、誰が弁護をしても、執行猶予の判決(今回のことで直ちに刑務所に行く必要はないが、判決で決められた期間の中で、新たに別の事件を起こした場合には、新しい件と今回の件(覚せい剤)の両方について刑務所に行く可能性があるという判決)が出ることがほぼ確実に予測されます。
たとえば、このような事件で、捕まっている人から、寂しいから毎日会いに来てもらいたいとか、毎日新しいマンガを差し入れしに来てもらいたい、という要望が出たとします。
国選弁護人であれば、そのような要望に100%応えることはできないと思います。
他方で、私選弁護人であれば、そのような要望にも全て応じてくれるかもしれません。
これは、刑事裁判における弁護の内容や本人の防御権とは、基本的に関係が無い事項であるからです。
私個人の感覚ですが、国選と私選の違いは、弁護の内容や本人の防御権と関係のないところで、出ることが多いのではないかと思います。
また、国選と私選で違いが大きく出るとすれば、弁護士のやる気ではなく、弁護士の力量でしょう。
逮捕された理由となる事実を否認しているような事件では、裁判で、当該犯罪行為があったかどうかが激しく争われます。
そのような場合には、刑事弁護に精通した私選弁護人を選任することが、本人の防御に大変資することになると思われます。
静岡を拠点に活動する弁護士の石川アトムと申します。静岡市に育ち、大学時代に祖母が交通事故に遭ったことをきっかけに、人の人生の大切な一歩を支えたい気持ちが芽生えました。東北大学法学部や京都大学法科大学院で学び、地元で弁護士として働きたい想いを胸に、2022年に独立開業し、石川アトム法律事務所を立ち上げました。事件の進行状況や今後の見通しをこまめに伝えるよう心がけ、ご相談者さまの安心につながればと思っています。趣味は英会話。
弁護士14年目で振り返る弁護士1年目の“アレ”
弁護士の「考える力」
皆様、こんにちは。弁護士の石川アトムです。
当事務所のブログは概ね0の付く日に更新されています。
本当は、2024年1月1日に、書き貯めている記事のうちの1つをアップしていいにしようかと思っていたのですが、予定を変更して、2023年最後の1本を書くことにしました。
きっかけは、静岡法律事務所の忘年会にお招きいただいたことです。
静岡法律事務所は、私が約12年在籍していた静岡市にある法律事務所で、多数の弁護士が在籍しています。
独立後も、忘年会にお声掛けいただき、大変有り難く思っています。
さて、その忘年会の中で、ベテランの弁護士がルーキーイヤーを終えたばかりの弁護士に対して、「何でもかんでも質問してこないで、まずは自分でちゃんと調べなさい。」と教え諭す一幕がありました。
このご意見については、全く同感です。
そもそも弁護士は、分からないことが多いのです。
裁判官だって判断に迷うことがあるのです(これらに関する詳しい内容は、こちらの記事をご覧ください)。
以前の記事は、交通事故の過失割合に関するお話でした。
交通事故の過失割合に限らず、弁護士は分からないことに行き当たったとき、文献に当たる、裁判例を検索するなどして、まずは自分で調べます。
「全く一緒」の事例があったとしても、その事例が本件で使えるかどうかについて検討が必要です。
果たして本件をその事例と同様に考えて良いかどうかを考えるわけです。
全く一緒の事例がなければ、似たような事例から、問題となっている事件の結論を推論することになります。
共通点は何か、違う点は何か、共通点は本件で有利に働くのか不利に働くのか、違う点は本件で有利に働くのか、不利に働くのかを考えます。
似たような事例すら無ければ、自らの“常識”、感覚に従って結論を推論します。
ここでいう“常識”は、法的な結論を導くための“常識”です。
こういう場合にはこういう結論になることが法的なバランス感覚からして妥当なのではないか、というものです。
繰り返しになってしまいますが、弁護士でも、裁判官でも、答えが分からないことも多いのです。
唯一の答えなど無いことの方が多いのです(三審制という制度を考えても、そのことは明らかでしょう)。
弁護士として成長するためには、まずは、自分で調べて、考えてみるということが必要であろうと思います。
そして、その積み重ねが、考える力を磨き、弁護士としての実力を養っていくものだと思います。
弁護士1年目の“アレ”とは
静岡法律事務所の忘年会での一幕を妻に話したところ、「OJTは無いの?」という話が出ました。
静岡法律事務所では、私が弁護士として入所した頃から、私が独立するまでの間、1年目の弁護士は、先輩の弁護士とともに事件を共同で受任し、先輩の弁護士とともに事件を進めていくというやり方をしていました。
おそらく現在も、同様の手法が採られているのでしょう。
このように、弁護士1年目は、基本的には先輩弁護士とともに事件に取り組みます。
しかし、先輩弁護士が、その事件についてアレコレと教えてくれることは基本的にはありませんでした。
概要として、この事件は交通事故で後遺障害が認められてね、とか、この事件の依頼者は不貞の相手方でね、とか、その程度のアナウンスはあったように思います。
しかし、あとは、自分でどう事件を進めていくか考えて、依頼者と打合せをしながら進めていく、付け足しや訂正があれば、先輩弁護士が依頼者に聴き取り等をして修正していくというような感じであったと思います。
習うより慣れろ、というわけです。
さて、先輩弁護士の中に特徴的な指導をされる方がいらっしゃいまして、忘年会の最中にそのことを思い出しました。
その先輩弁護士の指導方法は、「先に打合せ進めといて」というものでした。
1年目で(というか、弁護士登録数日で)右も左も分からない状態で、依頼者とも初対面。
「先に打合せ進めといて」は、なかなかの恐怖でした。
新人の飼育員が、先輩から、「君、トラの体温計っといて」といきなり言われるような感覚でしょうか。
仮に私が弁護士を雇う立場になってもそういう指導はしませんが(依頼者は、「弁護士石川」に事件を依頼してくださっていると思いますので)、新人教育としては、ある意味、一番実践的だったかもしれません。
ただ、それも、自分で考えたり、調べたりすることを当然の前提として理解している新人に当てはまることだと思いますが。
旧所属先の忘年会に参加し、弁護士1年目の「先に打合せ進めといて」=私にとっての“アレ”を久しぶりに思い出しました。
静岡を拠点に活動する弁護士の石川アトムと申します。静岡市に育ち、大学時代に祖母が交通事故に遭ったことをきっかけに、人の人生の大切な一歩を支えたい気持ちが芽生えました。東北大学法学部や京都大学法科大学院で学び、地元で弁護士として働きたい想いを胸に、2022年に独立開業し、石川アトム法律事務所を立ち上げました。事件の進行状況や今後の見通しをこまめに伝えるよう心がけ、ご相談者さまの安心につながればと思っています。趣味は英会話。
弁護士14年目に入りました
12月15日は私が弁護士登録をした日です
皆様、こんにちは。弁護士の石川アトムです。
2023年も残り10日となりました。
皆様、いかがお過ごしでしょうか。
もう間もなくすると、2024年という新しい年が始まります。
人によって、色々な「新しい年」があると思います。
誰しもお持ちの区切りとしては、誕生日があるでしょう。
また、多くの会社やお役所では、4月1日が新しい年の始まりとなっていることでしょう。
私、弁護士石川にとっては、静岡法律事務所から独立し、新たに静岡市に法律事務所を開設した11月1日は、大きな節目の日です。
そしてもう一つ、私にとっての大きな節目の日は、私が弁護士登録をした12月15日です。
2023年12月15日、私にとっては、弁護士14年目となる新しい1年が始まりました。
毎年この時期になると、もうすぐ1年が終わるな、という感覚と、弁護士として新しい1年が始まったな、という2つの感覚を同時に持つことになります。
少し面白い感覚です。
私は、弁護士歴の分類として、「新人」、「若手」、「中堅」、「ベテラン」、「長老」という区切りを使っています。
これは、石川の個人的な分類です。
私の気持ち的には、私はまだ「若手」なのですが、さすがに14年目で「若手」はないですよね。
キャリアだけ見れば、立派に「中堅」と言っていいくらいの弁護士歴になりました。
この間、静岡県弁護士会が行っている破産管財人養成講座という講座に出席してきました(破産管財人については、こちらのページに詳しい内容がございます)。
この講座は、若手の弁護士に対して、破産管財実務を習得させることを目的として行っているものです。
破産管財実務についてある程度キャリアのある弁護士を、若手に対する指導担当として付け、指導担当の弁護士が若手の弁護士と一緒に破産管財事件を扱い、若手の弁護士にその内容を報告してもらっています。
私は、若手を指導する立場として、破産管財人養成講座に出席してきたのですが、その会の冒頭、指導担当の弁護士について、「ベテランの先生方」と紹介されていました。
私以外の先生方は「ベテラン」で差し支えないと思いますが、私は、まだまだ「ベテラン」と言われる歴には達していないのではないかと苦笑しました。
13年という期間は、長いようで、あっという間でした。
私はまだ30代なので、今後、弁護士として、「13年」を少なくともあと2回はやるでしょう。
そうすると、まだまだ今いる地点は、弁護士としてのキャリアの3分の1にしか当たらないわけですね。
「一生」という単位で考えると、「13年」をあと2回やって弁護士を引退した時点で、まだ人生は3分の1残っているわけで、何だか恐ろしいですね・・・。
30代なので当然かもしれませんが、まだまだ人生は先が長いです。
先輩弁護士の名言
私が弁護士なりたての頃、ある先輩の弁護士が、こんなことを言っていました。
「これから、皆さんは、弁護士としての道を歩まれていきます。
弁護士として仕事をしていく中で、とても辛く、大変なことがあると思います。
でも大丈夫です!!
その辛く、大変なことがあった後、もっと辛く、大変なことがあります!
だから、そのとき直面している辛く、大変なことは大したことではないのです!!!」
当時、その先輩の弁護士は、弁護士歴2、3年目とかだったと思いますが、14年目の私からしても、なるほど、その通り!!と思わずにはいられない名言です。
私はこれまで、あまり業務上ストレスを感じたことがなかったのですが(もちろん全く感じなかったわけではないですが)、今年はタフな一年でした。
でも、色々あった後に、次々と色々あったものですから、今では、そのほとんどは、「大したことなかったな」と思えてしまいます(笑)
来年の今頃も、「今年も色々あったけど、大したことなかったな」と思えるといいなと思います。
もう一つの新しいこと~事務局体制の変更
さて、先に12月15日に弁護士としての新しい1年が始まりました、というお話をしたのですが、最近、うちの事務所では、もう一つ新しいことがありました。
2022年11月1日の開所以来、石川アトム法律事務所を支えてくれた事務員さんが本日付で退職されることになりました。
同事務員さんには、裁判所への外回り、電話対応、来客対応、書類の作成補助など、それはそれはたくさんの業務を行っていただき、その事務員さん無しには、円滑な弁護士業務はできませんでした。
本当に助けていただきました。
ありがとうございました。
さて、そんなわけで、今後(特に2024年から)、石川アトム法律事務所では、新しい事務員さん2名をお迎えし、業務を行って参ります。
新しい2名は、ともに法律事務所での職務経験がなく、皆様にはご不便をお掛けすることがあるかもしれませんが、何卒ご容赦いただきたくお願い申し上げます。
弁護士石川も、これまで以上に、法的サービスの向上に努めて参りますので、2024年もどうぞよろしくお願いいたします(当事務所の年末年始のお休みについては、こちらの記事をご覧ください)。
静岡を拠点に活動する弁護士の石川アトムと申します。静岡市に育ち、大学時代に祖母が交通事故に遭ったことをきっかけに、人の人生の大切な一歩を支えたい気持ちが芽生えました。東北大学法学部や京都大学法科大学院で学び、地元で弁護士として働きたい想いを胸に、2022年に独立開業し、石川アトム法律事務所を立ち上げました。事件の進行状況や今後の見通しをこまめに伝えるよう心がけ、ご相談者さまの安心につながればと思っています。趣味は英会話。
2023年 弁護士石川が今年読んだ本の話2
隆慶一郎さんの「一夢庵風流記」
皆さん、こんにちは。弁護士の石川アトムです。
2023年もいよいよ残り20日余りとなりました。
私自身も、非常に重たい書類を何とか締め切りまでに書き上げ、今年の仕事の峠は越えたかなという感覚でおります(石川アトム法律事務所の年末年始のお休みについては、こちらの記事をご覧ください)。
さて今回は、弁護士石川が2023年に読んだ本の第2弾です。
早速ですが、私が今年読んだ本の中で、2番目に面白かった本は、こちらです。
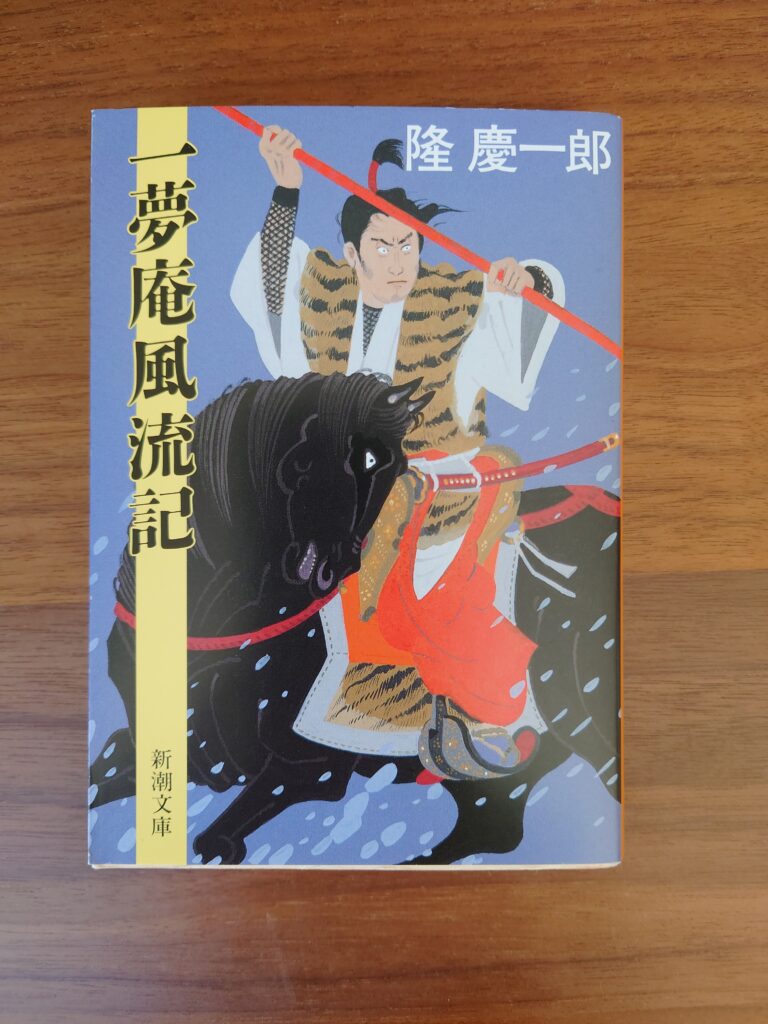
隆慶一郎さんの「一夢庵風流記」です。
タイトルだけをぱっと見ると、一体どこで区切って読めばいいのだろうと思われるかもしれません。
「一夢庵風流記」は、戦国時代末期に存在した前田慶次(あるいは前田慶次郎)という男性の人生を描いた歴史長編小説です。
男性には、「花の慶次」の原作です、とご紹介差し上げるのが最も分かりやすいでしょう。
インターネットを検索してみたところ、どうやら「花の慶次」には、「花の慶次」単体の公式サイトがあるようでして、そのリンクを貼らせていただきます。
加賀百万石で有名な前田利家は、前田慶次の義理の叔父という関係にあたります。
前田慶次のやることなすこと、とんちが効いた天晴れな所業に胸がすーっとします。
まさに、痛快な小説です。
元々、この本の作者である隆慶一郎さんの「影武者徳川家康」を読んだことがあり、隆慶一郎さんの本で、面白そうなものはないかなと思っていたところ、「一夢庵風流記」という本があることを知りました。
歴史ものが好きで、痛快な小説をお読みになりたい方には、是非おすすめの一冊です。
隆慶一郎さんの「影武者徳川家康」
「影武者徳川家康」は、関ヶ原の合戦で、家康は死んでおり、以後の家康は、家康の影武者あった世良田二郎三郎が家康に成り代わっているという物語です。
関ヶ原前には、「ただの影武者」に過ぎなかった世良田二郎三郎が、家康の子である秀忠や、一部の徳川家重臣に、家康の死を伝えつつ、対外的には自身が家康であるとして振る舞い、用済みとなった自身を亡き者にしようとする秀忠とどのように対峙していくかというストーリーです。
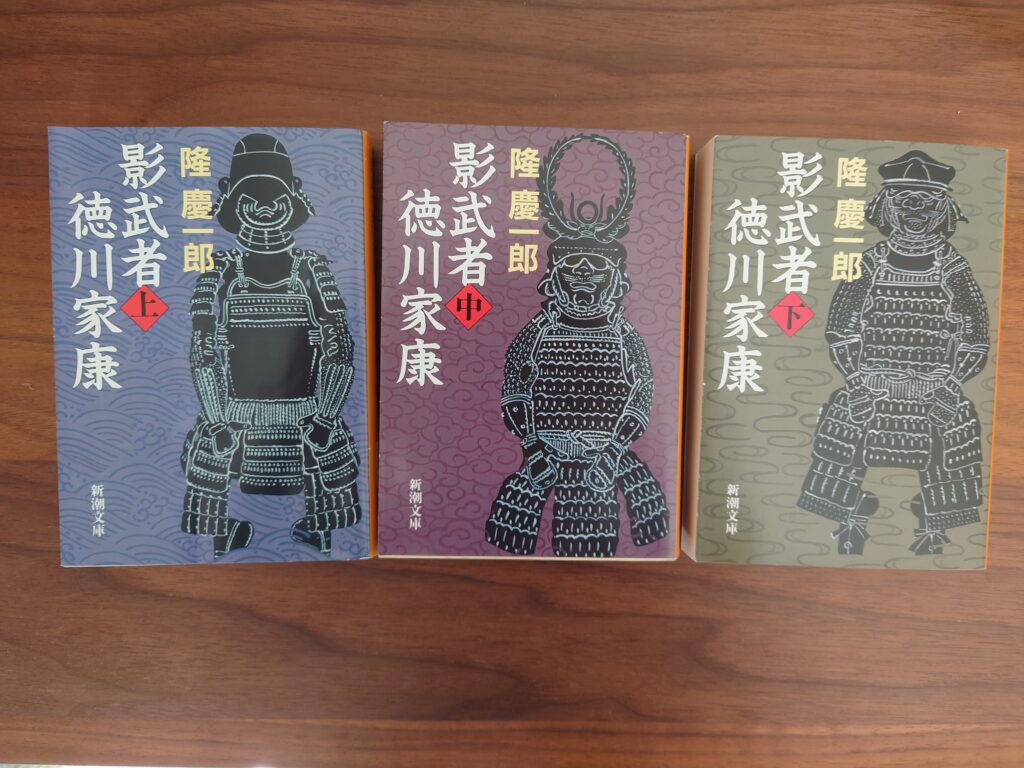
文庫版は、上中下3巻で1800ページを超える大作ですが、「一夢庵風流記」と同様に、さらっとした口当たりの本で、サクサク読めてしまいます。
「影武者徳川家康」は、同名のテレビドラマを見たのがきっかけで、中学のころに読みました。
それから24年経って、昨年何となくもう一度読んでみたいと思い、1800ページを一気読みしました。
こちらも是非お薦めしたい一冊(三冊)です。
東野圭吾さんの「ラプラスの魔女」
言わずと知れた東野圭吾さんですが、今年私が読んだのは、「ラプラスの魔女」とその前日譚にあたる「魔力の胎動」です。
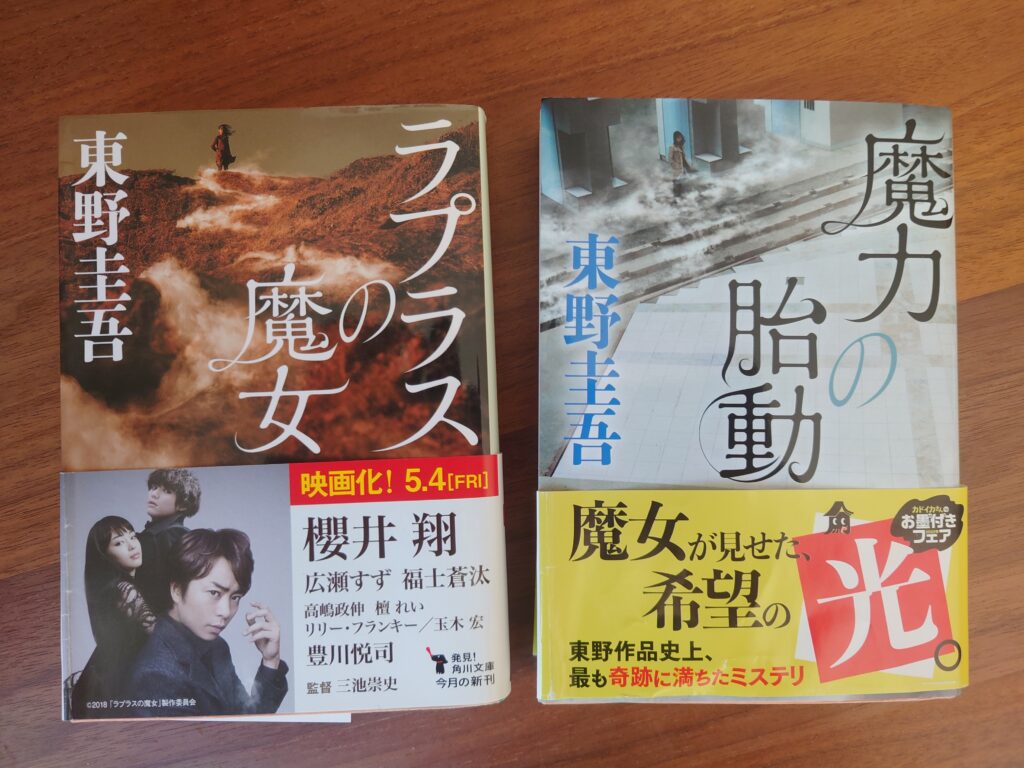
これらの2冊は、羽原円華という少女が主人公となっている小説です。
羽原円華には、気候状況や物や人の動き方について膨大なデータを学習し、今後の天気を物理法則に基づいて極めて正確に、かつ、緻密に予測したり、気体を含む物や人の動き方を予測したりすることができるという特殊能力を有しています。
「魔力の胎動」で出てくる例で言えば、天候を予測していつのタイミングで飛ぶのがスキージャンパーにとって最も良い風であるかといったことや、ナックルボールの軌道を計算して適確に捕球したりすることができる、ということです。
同じ東野圭吾さんの作品でも、ガリレオシリーズでは、湯川博士が色々と試行錯誤を重ねて実験をしていると思うのですが、羽原円華は、いわば、「秒で」答えを出してしまいます。
スーパーコンピューター富岳のような感じでしょうか。
先に小説の帯を見てしまったからかもしれませんが、小説を読んでいる最中の羽原円華のビジュアルイメージは、そのまんま、広瀬すずさんでした。
このシリーズでは、今年の3月に「魔女と過ごした七日間」という新作が公刊されています。
「ラプラスの魔女」も「魔力の胎動」も文庫本を買ったので、できれば文庫本が出るまで待ちたいのですが、多分我慢できずにハードカバーを買ってしまうでしょう。
その良い例が、東野圭吾さんの加賀恭一郎シリーズです。
加賀恭一郎シリーズは、司法修習生のときにドラマ「新参者」を見て、そのシリーズを知り、第一作の「卒業」から第七作の「赤い指」までは文庫本を購入していました。
しかし、「新参者」以降は、中古ですが、ハードカバーを購入しています。
「新参者」が文庫本化されたのは、ハードカバーの発売から4年後で、その後も文庫本化には概ね3年がかかっています。
そんなに待てません!!
というわけで、今年の9月発売の加賀恭一郎シリーズ最新作「あなたが誰かを殺した」を楽天ラクマで購入してしまいました。
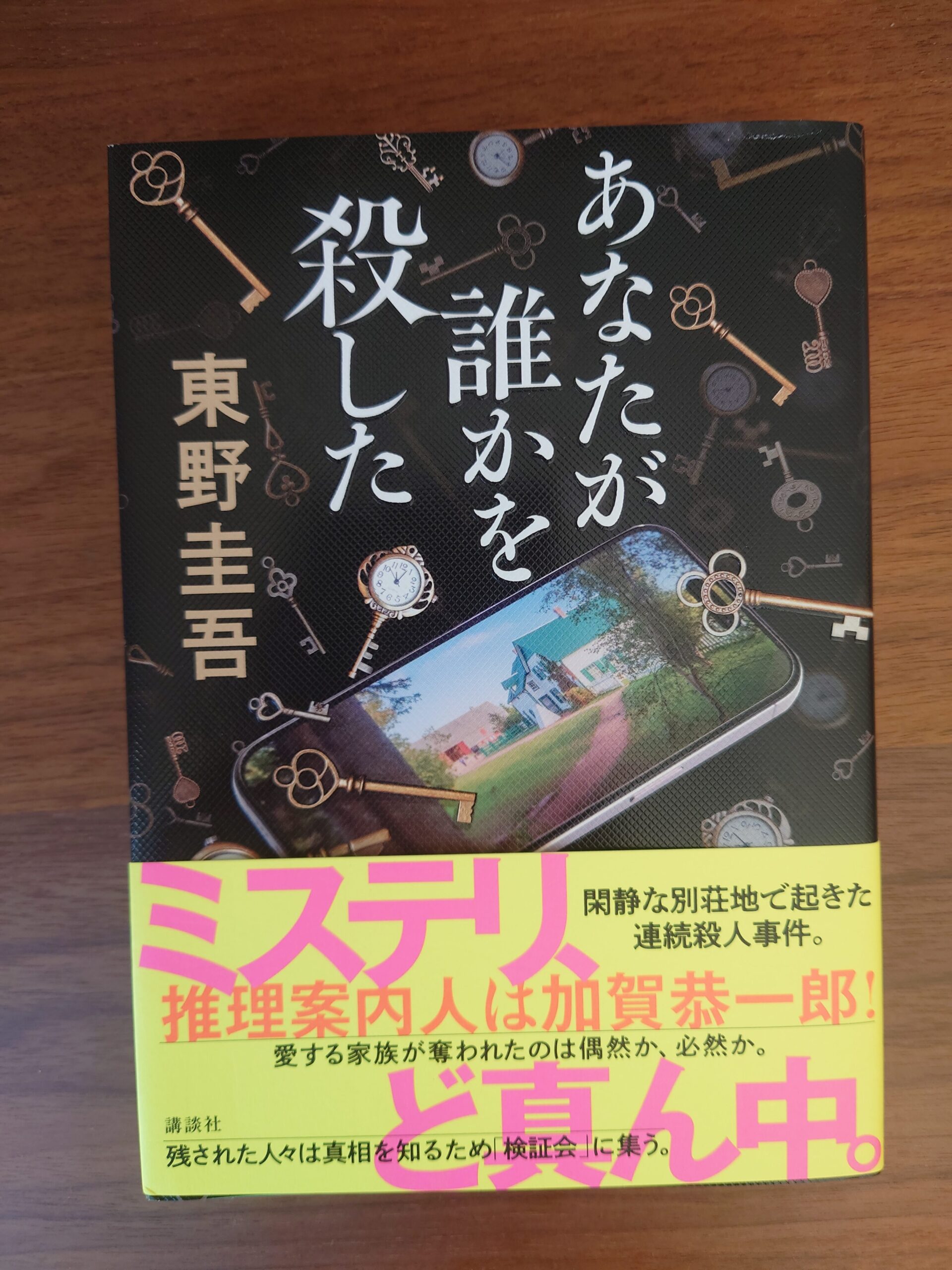

年末年始のお休みに読もうと、今からとてもワクワクしています。
静岡を拠点に活動する弁護士の石川アトムと申します。静岡市に育ち、大学時代に祖母が交通事故に遭ったことをきっかけに、人の人生の大切な一歩を支えたい気持ちが芽生えました。東北大学法学部や京都大学法科大学院で学び、地元で弁護士として働きたい想いを胸に、2022年に独立開業し、石川アトム法律事務所を立ち上げました。事件の進行状況や今後の見通しをこまめに伝えるよう心がけ、ご相談者さまの安心につながればと思っています。趣味は英会話。
2023年 弁護士石川が今年読んだ本の話1
先輩弁護士からのプレゼントにより読書熱が再燃
皆さん、こんにちは。弁護士の石川アトムです。
2023年もいよいよ残り1月となりました。
皆様におかれましては、年末年始のご準備をされている時期かと思います(石川アトム法律事務所の年末年始のお休みについては、こちらの記事をご覧ください)。
今回は、弁護士石川が2023年に読んだ本について紹介したいと思います。
元々読書が趣味だったのですが、今年の年明けから春先まで、花粉症の鼻づまりもあり、スッキリ眠れない日が続き、睡眠を重視して、あまり読書をしていませんでした。
しかし、いつもお世話になっている先輩弁護士から、小説「優駿」をプレゼントしていただき、これが大変面白く、読書熱が再燃しました(先輩弁護士からのプレゼントの話は、こちらの記事をご覧ください)。
2023年 最も面白かった本 ~ジョージオーウェル「1984年」
さて、さっそくですが、「優駿」以外で、私が今年読んだ本の中で、最も面白かった本の第一位は、こちらです。

ジョージ・オーウェルの「1984年」。訳者は高橋和久さんです。
以下、なるべくネタバレはしないように気を付けてはいますが、結論の方向性はネタバレがあります。
ご注意ください。
全体主義社会、監視社会の近未来を描いたディストピアノベルの金字塔と言われている作品です。
また、イギリスのある調査では、イギリス人が読んだことのあるフリをした本の第一位にもなったことがあるようです(笑)
出版は1949年で、そのうえでの「近未来」を描いた作品なのですが、1949年出版ということを全く感じさせない、むしろ最近書かれたんじゃないかと思ってしまうような作品です。
「テレスクリーン」という一方通行の監視カメラ、監視スクリーン的な装置など、現代でもあり得そうな設備が出てきます。
出版年以降に、実際に某国で行われていたことが書かれているのではないかと思われるような迫真さと、ある意味の現実感がありました。
そして、この本は、「あーー、ダメダメ。そっち行っちゃダメ。あ~あ・・・」というような主人公の言動で、一体この先どうなっちゃうの、というハラハラ感が止まりません。
さらに、クライマックスに訪れる、突然、足下の床が無くなって垂直落下するようなフリーフォール感と絶望感。
さらに、その後の、ふわふわ感(「何も無かったことにする感」に近いかもしれません)。
読み応え抜群です。
「1984年」に登場する「ニュースピーク」
「1984年」は、とてもお薦めな本なのですが、この本にはちょっと取っつきにくいところがあります。
私も実際、最初の数ページを読んで数か月寝かせるということをこれまで2度ほどしたと思います。
先ほども若干紹介した「テレスクリーン」以外にも、この本で用いられている設定や、それを表す語彙に慣れるまでちょっと時間がかかるかもしれません。
小説中には、「オセアニア」、「ユーラシア」、「イースタシア」という国名が登場します。
しかし、小説に出てくる「オセアニア」や「ユーラシア」は、現在私たちが使っている「オセアニア」や「ユーラシア」とは異なっています。
これがまたややこしい。
小説中の「オセアニア」は、概ね南北中央アメリカ、イギリス、オーストラリア、アフリカ南部を含む地域で、本小説の主人公は、「オセアニア」で暮らしています。
「ユーラシア」はロシア+ヨーロッパ、「イースタシア」は、概ね、中国、モンゴル、チベット、日本、東南アジアの地域を意味しています。
また、私の場合、特に「ニュースピーク」という設定に混乱しました。
「ニュースピーク」は、カタカナで書かれていたこともあって、この本の相当途中まで、
「new speak」=新しい言語ではなく、「News peak」=とっておきのニュースだと思っていました。
ニュースピークというのは、この小説に登場する、いわば新しい英語のことです。
ニュースピークの目的は、言葉の数を減らしていくことです。
たとえば、現在の英語には、「寒い」を意味する「cold」という言葉があり、温かいには、
「warm」という言葉があります。
しかし、ニュースピークに「warm」という言葉は存在しません。
「寒い」=「cold」に「非」を意味する接頭語「un-」がプラスされ、「uncold」が「warm」の代わりを果たします。
このように、代替可能な語彙は、次々と一つの語にまとめられ、消滅していきます。
人は、言葉を失うと、その事実を適確に表現したり、考えたりすることができなくなります。
そのように、言葉を奪っていくことで、支配層にとって不都合な思考自体をさせないようにしていく、というのがニュースピークの目的です。
なるほど確かに、言葉を奪われてしまうと、考えること自体ができなくなってしまいます。
その思考を指し示す表現ができなくなってしまうのです。
この発想には、よくまぁそんなこと考えたなぁと感服しました。
「1984年」、とてもお薦めです。
年末年始のお休み中にいかがでしょうか。
静岡を拠点に活動する弁護士の石川アトムと申します。静岡市に育ち、大学時代に祖母が交通事故に遭ったことをきっかけに、人の人生の大切な一歩を支えたい気持ちが芽生えました。東北大学法学部や京都大学法科大学院で学び、地元で弁護士として働きたい想いを胸に、2022年に独立開業し、石川アトム法律事務所を立ち上げました。事件の進行状況や今後の見通しをこまめに伝えるよう心がけ、ご相談者さまの安心につながればと思っています。趣味は英会話。
年末年始のお休みのお知らせと、弁護士業務の繁忙期・閑散期
石川アトム法律事務所の年末年始のお休み
皆さん、こんにちは。弁護士の石川アトムです。
2023年も残すところ、40日余りとなりました。
本年も皆様のおかげで、何とか1年業務をこなすことができそうです。
ありがとうございました。
さて、石川アトム法律事務所では、2023年12月28日(木)から2024年1月8日(月祝)まで年末年始のお休みをいただきます。
2023年の最終営業日は12月27日(水)、2024年、年明けの最初の営業日は、1月9日(火)の予定です。
上記お休みの期間中、私が(弁護士が)気まぐれで事務所に来て仕事をしていることがあるかもしれませんが、基本的には、事務所にお電話をいただきましても、ご用件を承ることができません。
何卒ご了承ください。
他方で、法律顧問のご用命をいただいております顧問企業様におかれましては、年末年始の間も、何かございましたら、いつでも当職の携帯電話宛てにご連絡をいただければと思います(法律顧問、顧問契約等に関心がございましたら、こちらのページをご覧ください)。
少し気が早いですが、本ブログの読者の皆様におかれましては、どうぞ良いお年をお迎えください。
私も2023年、ラストスパートで頑張って参ります。
弁護士業務の繁忙期
弁護士をしておりますと、「ご専門は何ですか。」という、実は、回答に困る質問をいただくことが多いというお話を、以前別の記事で書きました(ご興味がございましたら、「弁護士の専門分野??」の記事をご覧ください)。
私がよく尋ねられる質問の1番は、「本名ですか?」ですが、2番は、「専門分野は何ですか?」です。
これらに続くと思われるのが、「弁護士はいつが忙しいんですか?」「弁護士も年末年始は忙しいんですか?」というご質問だと思われます。
このご質問に対しては、「12月、1月というように、毎年同じ時期が忙しいということはありませんが、逆に、年度末(3月末、4月頭)は、ヒマな場合が多いです。」というお答えを差し上げることが多いと思います。
弁護士の仕事の中には、ある程度スケジュールを調整できるものもありますが、調整できないものが多いと思います。
この事件が来ると、途端に忙しくなるという事件類型の一つに、会社の自己破産があります。
特に、まだ事業を続けている会社を急遽破産させることにする、という場面は、かなり忙しくなります。
個人の自己破産や、既に事業を停止している会社の自己破産が、「1か月に一度通院してくださいね。じゃあ、来月は15日に来てください」というイメージであるとすれば、会社の自己破産は、救急車で患者さんが運ばれてきて、その患者さんの全身にわたって、様々な手術や治療を順番立てて早急に行っていかなければならない、というイメージでしょうか。
まだ事業を続けている会社の自己破産手続をご依頼いただきますと、業務はかなり忙しくなります。
他方で、そういった自己破産の事件の依頼は、いつ来るか全く分かりません。
それほど急激に忙しくなるわけではありませんが、個人の自己破産、交通事故の賠償請求のご依頼も同様に、いつご依頼をいただけるのか全く分かりません。
会社や個人が自己破産手続を取るかどうか、それを弁護士に相談するかどうかは、基本的には、各会社や個人が決断するものですし、交通事故に至っては全くの偶然により発生するものです。
いつどのような依頼が来るか分からないため、弁護士業務の繁忙期は、年末年始、1月、などというように、毎年決まった時期というものがありません。
弁護士業務の閑散期
弁護士がいつ忙しくなるのか、については、毎年決まった期間があるわけではありませんが、弁護士がいつ比較的ヒマになるのか、ということについては、私は年度末、年度初めだろうと思っています。
日本の裁判所には、簡易裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、高等裁判所、最高裁判所という種類があります。
裁判業務を取り扱っている多くの弁護士にとって(実は、世の中には、裁判業務を全く取り扱わない、裁判所に行ったことがないという弁護士もいます!)、受け持っている裁判の多くは、地方裁判所か家庭裁判所の事件であろうと思います。
裁判手続を取り仕切るのは、誰でしょうか。
当然裁判官です。
裁判官は公務員であり、転勤があります。
裁判官は概ね3年毎に転勤をします。
そして、地方裁判所、家庭裁判所の裁判官が転勤するのは、通常年度末、年度明けです。
裁判官には、2月ころまでには内示が出るようで、その裁判所に残るのか、別の裁判所に行くのかが分かります。
裁判は概ね1月に1回程度行われるのですが、2月の時点で、来年度は転勤をするため、今の裁判所にはいないということが分かると、その事件については、年度末、年度初めに裁判を入れることができなくなります。
年度末に入れても裁判官はいませんし、年度初めに入れてしまうと、来たばかりの裁判官が膨大な記録に目を通すことが間に合わず、意味のない期日になってしまうからです。
このような理由で、転勤が決まっている裁判官の事件については、年度末、年度初めの時期に裁判は行われません。
年度末、年度初めは、期日が減るため、弁護士としても、比較的のんびりと仕事をすることができるのです。
静岡を拠点に活動する弁護士の石川アトムと申します。静岡市に育ち、大学時代に祖母が交通事故に遭ったことをきっかけに、人の人生の大切な一歩を支えたい気持ちが芽生えました。東北大学法学部や京都大学法科大学院で学び、地元で弁護士として働きたい想いを胸に、2022年に独立開業し、石川アトム法律事務所を立ち上げました。事件の進行状況や今後の見通しをこまめに伝えるよう心がけ、ご相談者さまの安心につながればと思っています。趣味は英会話。
弁護士の出張~静岡県外でのお仕事
仕事の中心は静岡県内
みなさん、こんにちは。弁護士の石川です。
今日は、私の弁護士としての、地理的な意味での仕事の範囲についてお話ししたいと思います。
と言いますのも、ここ最近、静岡県外へ出向く機会が多かったためです。
地理的な意味での、私の仕事の中心は、静岡市、藤枝市、焼津市などを中心とする静岡県中部地区です。
当法律事務所が静岡市に位置していることもあり、静岡市、藤枝市、焼津市にお住まいのお客様からご依頼をいただくことがほとんどです。
静岡県中部にお住まいの方からご依頼をいただくと、多くの場合、事件を取り扱う裁判所も静岡市にある静岡地方裁判所になります。
自己破産の申立ては、申立人(破産者)の住所地を管轄する裁判所に申立てをします。
交通事故による損害賠償請求の裁判を提起する場合、依頼者(原告)の住所地を管轄する裁判所に訴訟を提起することが通常です。
私が現在扱っている事件の7割程度は、静岡市にある静岡地方裁判所で審理されています。
残りの3割が、同じ静岡県内にある静岡地方裁判所の浜松支部であったり、沼津支部であったり、県外の裁判所であったり、という感じです。
このように、弁護士としての私の仕事は、静岡市や静岡県中部地区での仕事がメインです。
静岡県外での仕事
時々ですが、静岡県外に出張をすることもあります。
県外出張をする1つ目のケースは、静岡地方裁判所(沼津支部や浜松支部を含みます)の判決に対して控訴したり、控訴されたりして、裁判が東京高等裁判所に進んだ場合です。
控訴したり、控訴されたりすることは、それほど多くはないため、東京高等裁判所に行くのは年に2、3回ほどです。
近時は、裁判手続もIT化が進んでおり、静岡地方裁判所の事件のほとんどは、Web会議を利用して行われています(裁判とWeb会議については、こちらの記事をご覧ください)。
そのため、裁判所に出向くことは稀で、ほとんどの手続は、事務所からインターネットを通じて進行されています。
これは、静岡県外の地方裁判所において審理されている事件も同様です。
現在の法制度では、裁判が尋問手続まで進行すると、裁判所に出向かなければなりませんが、そうでない限りは、Web会議で済んでしまいます。
他方で、現状、東京高等裁判所で開かれる第1回目の裁判は、裁判所へ行く必要があります。
しかし、来年の5月ころには、新しい法制度が施行され、東京高等裁判所の第1回目もWeb会議に切り替えられているかもしれません。
今後、東京高等裁判所へ出張することも無くなってしまうのでしょうか・・・。
県外出張をする2つ目のケースは、首都圏の顧問先企業のお仕事をするために、首都圏に出張するという場合です。
首都圏の顧問先企業とのお仕事は、通常、メール、電話、LINEなどで行っているため、現地に赴くことはそれほど多くありません。
年に1、2回あるかどうかという具合です。
「公示送達」のお話
先にお話しした2つのケースは、割と定型的な県外出張と言えます。
他方で、イレギュラーな県外出張もごく稀に発生します。
私が過去に行った最も遠かった出張先は、山陰地方の某所です。
だいぶ話が飛びますが、ここで、「公示送達」という制度について説明をさせてください。
原告が裁判を起こす際、原告は、裁判所に「訴状」という書類を提出します。
そして、裁判所は、相手方である被告に対して訴状を郵送します。
原則として、被告に訴状が届かないと裁判を始めることができません。
被告にも反論する機会を与える必要があるためです。
通常は、原告が把握している、被告が住んでいると思われる場所を訴状に記載して、裁判所に、当該住所宛てに訴状を送ってもらいます。
しかし、ときどき、被告が、原告が把握している場所とは別の場所に住んでいるということがあります。
そういった場合、新しい住所が分かれば、裁判所に対して、新しく分かった住所をお伝えして、訴状を送ってもらうようにします。
他方で、どれだけ調べてみても、新しい住所が分からないというケースもあります。
あるいは、そもそも被告の住所が分からないというケースもあります。
そのような場合に、被告の就業先が分かっていれば、例外的に、被告の就業先に訴状を送ってもらうということもあります。
ただし、会社に「あなた、訴えられてますよ!」ということが分かりかねない書類を送付した場合、被告の社会的(というより会社的でしょうか)信用を落とすことになりかねませんので、このような送達は、例外的です。
原則として、訴状は、被告が住んでいる所に送らなければいけないのです。
それでは、被告の住んでいる所も、就業先も分からないという場合、訴状の送達はどうしたら良いのでしょうか。
結論としては、裁判所の敷地内にある掲示板に、「あなた、訴えられてますよ!」という紙を貼って、訴状は相手方に送達された、ということにしてしまいます。
このような手続を「公示送達」といいます。
ただし、先ほどもお話ししましたように、被告には裁判で反論をする権利があり、そのためには、被告に裁判を起こされていることを知らせる=訴状を届ける必要があります。
多くの人にとって、裁判所の掲示板なんて通常見るものではありませんから、公示送達をするということは、被告が裁判において反論する機会を事実上閉ざしてしまうことになる、と言っても過言ではないでしょう。
原告の裁判を進めたいという権利と、被告の反論をする権利のバランスを取ったうえで、裁判手続を進める(公示送達をする)ということにするので、裁判所に公示送達をしてもらうことは、それなりにハードルが高いのです。
公示送達をしてもらうためには、原告は、できる限り、被告の所在を突き止める努力をする必要があります。
たとえば、現時点の住民票上の所在地に赴いて、その住所地にある家の表札であったり、アパートの郵便受けであったりに、被告の名前がないか確認をします。
また、郵便受けに郵便物が大量に投函されたままになっていたり、その家の電気のメーターが回転していなかったりして(電気が使用されていないということ)、被告の住所地とされる家に、人が住んでいる気配がないことを確認することもあります。
さらには、お隣さんにアポ無し訪問をして、「○○さんという方(被告)を最近見かけたことありますか。」、「お隣には、どなたか住んでいるのでしょうか。」などと聞き込みをすることもあります。
そして、このような調査結果をまとめた報告書を裁判所に提出し、原告としてできる限りの調査をしたけれど、被告の所在を突き止めることはできなかった、ということを裁判所に理解してもらうわけです。
公示送達の現地調査のため山陰某所への出張
私が山陰の某所に行ったのは、このような公示送達のための現地調査をするためでした。
現地に行かなければならなくなったときには、あまりに遠くて、「マジかよ、、、」と思いました。
しかし、実際には、弁護士1年そこそこであった当時、私は時間に余裕のある独身貴族でしたから、現地調査の「ついで」に、広島で野球の試合を見て一泊するなど、優雅な出張をしていました。

今はとてもそんな時間的余裕はありません。
先日、隣県某所へ行ってきたのですが、朝6時過ぎの新幹線で静岡を出て、9時半には静岡に戻っているという、まさにとんぼ返りな出張でした。
たまには、のんびりとした出張をしたいなぁと思う、今日この頃です。
静岡を拠点に活動する弁護士の石川アトムと申します。静岡市に育ち、大学時代に祖母が交通事故に遭ったことをきっかけに、人の人生の大切な一歩を支えたい気持ちが芽生えました。東北大学法学部や京都大学法科大学院で学び、地元で弁護士として働きたい想いを胸に、2022年に独立開業し、石川アトム法律事務所を立ち上げました。事件の進行状況や今後の見通しをこまめに伝えるよう心がけ、ご相談者さまの安心につながればと思っています。趣味は英会話。
石川アトム法律事務所は開所1周年を迎えました
オンライン英会話をやるほど暇だった当初3か月
皆さん、こんにちは。弁護士の石川アトムです。
石川アトム法律事務所は、本日、開所1周年を迎えました。
無事に開所1周年を迎えられましたこと、皆様に篤く御礼申し上げます。
開所3か月ほどはものすごく暇で、半日、一本の電話も鳴らないなんていうこともザラでした。
あまりに暇で、日中、事務所でオンライン英会話をやっている有様でした(もちろん事件記録等が一切画面に映らないような状態で、です)。
有り難いことに春ころから大変忙しくなり、その忙しさが今も続いています。
オンライン英会話なんてやっている時間はありません。
席の配置も影響していると思うのですが、事務員さんと私との間では会話がありません。
開所当初は、ほとんど電話も鳴らなかったものですから、お互い無言でパソコンを叩く音だけが半日聞こえる、ということもしばしばでした。
私はそのような無言の状況に気まずさを覚えつつ、かといって、積極的に事務員さんに話し掛けるわけでもなく過ごしていたのですが、おかげさまで忙しくなってからは、事務員さんとの間で業務上のやり取りが格段に増え、気まずさを覚えることは無くなりました。
破産、交通事故、顧問業務の3本柱が反映された1年
当事務所のホームページでは、自己破産、交通事故、顧問業務の3本を主な業務として掲示しています。
当事務所では、以前にご依頼をいただいた方や顧問先企業様からのご紹介案件が多く、ホームページを見てお問い合わせをいただくということは、それほど多くはありません。
しかし、ホームページをご覧いただいて、ご相談やご依頼をいただくお客様の多くは、自己破産や交通事故のご相談、ご依頼です。
自分がそのような案件をメインとして扱いたいという希望が反映された1年だったなと思います。
会社の破産申立て
また、この1年で特筆すべきは、複数の会社の破産申立て事件を扱ったことです。
独立する前(静岡法律事務所時代)は、私が会社の破産事件に関わるのは、申立ての場面ではなく、破産手続が開始された後の破産管財人として、という場面が圧倒的に多かったです(破産管財人が破産手続においてどのような立場にあるのかについては、こちらの記事をご覧ください)。
しかし、この1年は、複数の会社について自己破産申立てに関わることができました。
今後も、会社の自己破産申立てに関わることができればと思っています。
意外と見られているこのブログ
また、開所1年経って思うのは、よくこのブログを1年も続けることができたな、ということです。
当事務所では、概ね0の付く日に新しい記事をアップしています。
月に3回、年で言うと36回ということになります。
春以降忙しかった中で、ブログの更新を続けられたことはなかなか頑張ったなと思います。
そして、このブログ、意外と見られているようです。
顧問先の社長さんや裁判官もご覧になることがあるようです。
うかうかと、我が家の1月の食費は4万5000円だの、司法修習中のお昼は毎日レーズンパンだっただの、くだらないことばかり書いているわけにはいきませんね。
先日、妻に、ドラマ「きのう何食べた」に関連して、また食費の話をブログに書いた、と言ったら、「あなたは何を目指しているの!?」とお叱りを受けました(笑)
でも、多分、次の1年もこんな感じのブログになると思います。
開所1年を目前にしてようやく訪れることができたお店~もんや
当法律事務所の開所1年を目前にした、まさにギリギリセーフというタイミングでしたが、先日、当事務所と同じビルに入っている居酒屋「もんや」さんに行ってきました。
暗めの照明で落ち着いている一方、お客さんがたくさんいて、みなさん料理とお酒を楽しんでおり、温かい空気感のお店でした。
私がいただいたのは、お造りの盛り合わせ、桜えびの卵とじ、黒はんぺんフライなど、静岡の食材を使ったお料理で、どれも大変美味しかったです。
↓ お通しとビール。 とっても美味しい煮物でした。

↓ お造り1人前

↓ 桜えびの卵とじ 日本酒がすすみます!!

私はビールと日本酒が好きなのですが、日本酒も珍しい種類を扱ってらっしゃいました。
私がこの日いただいたのは、近日訪れようと思っている山形県の「楯野川 清流」と、2年ほど前に、妻がバレンタインデーにくれた「赤武 AKABU」です。
「赤武 AKABU」は岩手県のお酒のようです。
どちらも静岡ではあまり扱っているお店はないのではないでしょうか。
マスターともゆっくりお話ができました。
マスターは、先代のビル所有者とお知り合いで、ビルの竣工当時からお店を開いているということでした。
食べログ情報によると、開店25年のようです。
老舗の居酒屋さんですね。
マスターによると、当事務所の前に同じ階に入居されていたのは、何らかの事務所であったようです。
私が建物の内覧に訪れたときには、壁には何カ所も穴が開いているわ、床には手のひら大のピンクの染みが付いているわ、という状態で、私はてっきり飲食店が入っていたのかと思いました。
事務所って、一体何の事務所だったんでしょうね・・・。
静岡の美味しいものを食べたい方、美味しいお酒を飲みたい方、「もんや」さんは是非おすすめです。

静岡を拠点に活動する弁護士の石川アトムと申します。静岡市に育ち、大学時代に祖母が交通事故に遭ったことをきっかけに、人の人生の大切な一歩を支えたい気持ちが芽生えました。東北大学法学部や京都大学法科大学院で学び、地元で弁護士として働きたい想いを胸に、2022年に独立開業し、石川アトム法律事務所を立ち上げました。事件の進行状況や今後の見通しをこまめに伝えるよう心がけ、ご相談者さまの安心につながればと思っています。趣味は英会話。