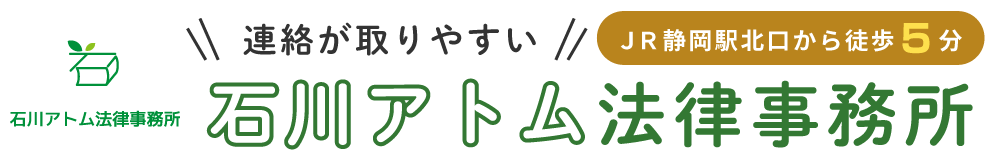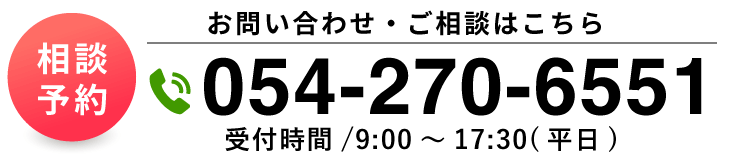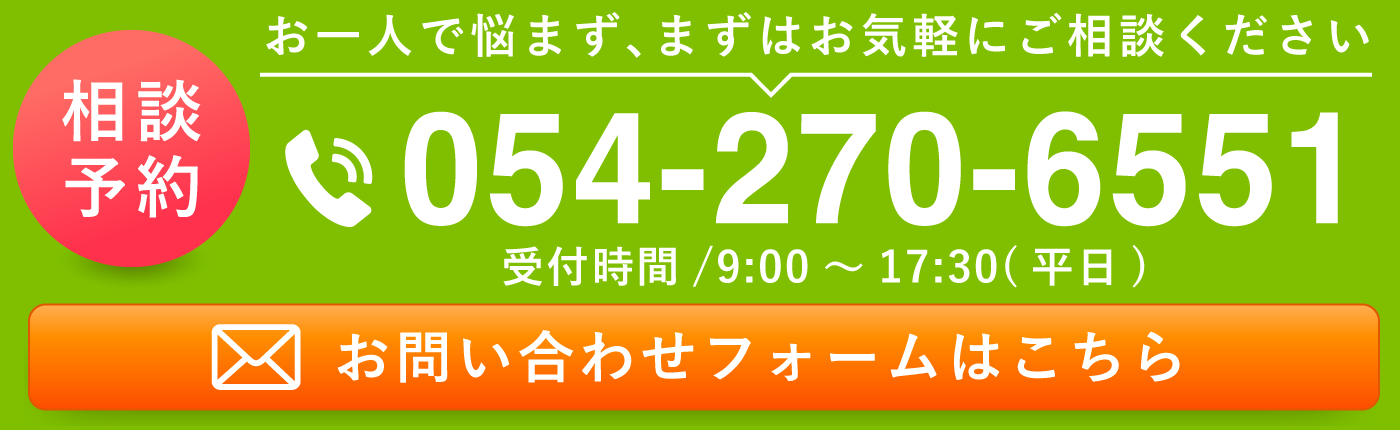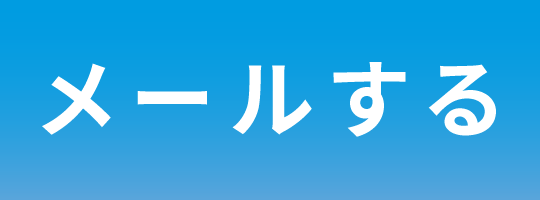このページの目次
民事裁判修習で最も勉強になったこと~裁判官も判断に迷う
民事裁判修習では、裁判官と一緒に裁判の場に臨んだり、裁判官室で、裁判をどのように進めていくのが良いか裁判官と協議をしたり、判決を出すとしたらどのような内容の判決を出すかということを起案したりしました。
私が民事裁判修習中に最も勉強になったことは、裁判官も判断に迷う、ということを知ることができたことです。
人間だもの、判断に迷うことなんてあるに決まっているじゃないか!
という感覚は、我々弁護士と、裁判実務に携わっていない一般の方と、どちらの方がしっくりくる感覚でしょうか。
裁判官の仕事の一つに、判決を書くということがあります。
裁判官は、ある事件に関して、最終的に、白か黒か、という判断を迫られることがあります。
判決文に裁判官の迷いが見られることは基本的にはありません。
しかし、内心では、判断に迷うことも少なくないのではないかと、私は思っています。
日本の裁判では、三審制が採られています。
地方裁判所の判決に対して不服があれば、高等裁判所の判断を仰ぐことができます。
数は多くはありませんが、地方裁判所の判断が高等裁判所でひっくり返ることもあります。
裁判官の判断は「絶対」ではないのです。
弁護士は「絶対勝てます!」と言ってはいけない
本ブログを閲覧されていらっしゃる方の中に、弁護士に相談をした経験がある方はいらっしゃいますでしょうか。
何か歯切れの悪い弁護士だったなぁ、という感想をお持ちかもしれません。
実は、弁護士は、「絶対勝てます!」などとは言ってはいけないのです。
弁護士には、守らなければいけない職務上のルールがあります。
そのルールの一つとして、依頼者に有利な結果を保証してはいけない、ということになっているからです。
しかし、私は、そのようなルールが無かったとしても、そもそも弁護士にとって、相談者や依頼者から話を聞いた段階で、結論を100パーセント見通せる事件というものは無いと思っています。
最初の相談の時から、「絶対勝てます!」などということは、言えないはずなのです。
弁護士が事件の結論を100パーセント見通すことができない事情
弁護士が事件の結論を100パーセント見通すことができない理由はいくつかあります。
理由の第1は、一方当事者の話しか聞いていないことです。
弁護士は、相談者の味方、依頼者の味方です。
通常、相談者、依頼者にとって最も利益になるような方向で助言をしたり、事件を進めたりします。
しかし、一方当事者の話しか聞けていない状態では、事件の見通しにも自ずから限界があります。
弁護士が事件の結論を100パーセント見通すことが難しい理由の第2は、「立証責任」というものがあるからです。
「立証責任」というのは、民事裁判において、「ある事実が存在する」ということを証明する責任のことです。
語弊を恐れず、非常にざっくり言えば、そのような事実があったと主張したい人が、そのような事実があったことを証明しなければなりません。
前回のブログでお話ししたように、民事裁判では、多くの場合、お金を請求するか、物の引渡しを請求します。
たとえば、配偶者と不貞行為を行った相手方に対して、慰謝料を請求するケースを考えてみましょう。
原告の配偶者も被告も不貞関係を否定している場合、原告は、被告と原告の配偶者が不貞関係にあったことを証明しなければなりません。
もっとも簡単な証明方法は、原告の配偶者と被告がラブホテルに入っていく様子を完璧に撮影した写真や動画でしょう。
次に考えられるのは、原告の配偶者と被告が、LINEで肉体関係があることを示すようなメッセージのやり取りをしている画面をスクリーンショットで撮影したものでしょうか。
しかし、これらの証拠が全く無いとした場合、その他の証拠により、どれだけ不貞行為の事実を証明できるのか、ということについては非常に予測が難しいと言えます。
ある事実があったかどうか、それを証明できる証拠として何があるのか。
これらのことは、事件の見通しを判断するうえで非常に重要ですが、同時に、予測が非常に難しい問題とも言えます。
弁護士が事件を100パーセント見通すことが難しい理由の第3は、同じ事件は2つとない、ということです。
たとえば、交通事故に基づく損害賠償請求事件を想定してみましょう。
交通事故に基づく損害賠償事件は、毎年全国で何百件、もしかすると、何千件と訴訟提起されています。
交通事故の場合は、相当数の裁判例の積み重ねがあります。
裁判例の積み重ねにより、ある程度確実性の高い見通しを持つことが可能であることもあります。
たとえば、交差点で、青信号で直進した自動二輪車と、対向車線を青信号で右折した自動車というようなケースでは、原則的な過失割合は○:○と定まっています。
双方の運転手において、例外的な落ち度がなければ、このような見通しの確実性は高いと言えます。
「原則的な」と書いたのは、この趣旨です。
しかし、交通事故の態様は、上記のような典型的なものばかりではありません。
たとえば、高速道路の料金所手前の合流車線で同一方向の車両同士が接触した、というようなイレギュラーな事故も当然存在します。
この場合には、直ちに「原則的な過失割合は○:○」とは分かりません。
このような場合、私はまず裁判例を検索します。
私が使っている裁判例の検索システムでは、「交通事故」「料金所」といった検索ワードで裁判例を検索すると110件の裁判例がヒットします。
これを全て閲覧して、類似事案が無いかどうかを探します。
裁判実務においては、類似事件の裁判例があるかどうかということは、訴訟を進めるうえでとても重要だと思います。
その判決が、最高裁判決なのか、高等裁判所の判決なのか、地方裁判所の判決なのかによって、効力というか、迫力というか、大分変わってくると思いますが、あまり前例がないような事件では、地方裁判所レベルの判決でも、裁判例が見つかると大変心強いものです。
他方で、裁判例が見つかっても、相談者や依頼者にとって、不利に働く可能性が高い場合があります。
また、そもそも同一態様の事故に関する裁判例を見つけることができない場合もあります。
そのような場合には、似たような事故の過失割合を転用できないかを考えます。
高速道路の料金所手前の合流車線で同一方向の車両同士が接触した、というケースで言えば、同一方向へ進む2つの車両のうちの一方が、進路変更して他方車両側に入ってきたと評価できないかといったことを検討します。
しかし、当然のことながら、このような検討を経た結果については、結論は絶対こうなります、などとは言えません。
「絶対勝てます!」などという弁護士にはご注意ください
このように、弁護士において、相談や依頼の際、ある程度の見通しを立てることはできますが、100パーセント結論を見通せる事件というものはありません。
「絶対勝てます!」などとは、言えないはずなのです。
裁判官が判断をする段階では、一方当事者の話しか聞いていないので、事件の見通しに限界があるという状況にはありません。
それでも、裁判官は判断に迷うようです。
もちろん事案によりけりですが、個人的には、裁判官も、ある事実があったと認めるかどうか、立証責任(上記理由の第2)のところで判断に迷うことが多いのではないか、と考えています。
静岡市を拠点に活動する弁護士。実務に入り16年目。
中心的な取扱分野は、会社個人を問わず自己破産申立事件。
裁判所の選任により年に数件の破産管財人も担当している。
また、会社の顧問弁護士として会社からの相談を受けることも多い(静岡県外(首都圏)にも複数の顧問先会社がある)。
趣味は旅行、英会話、競馬。