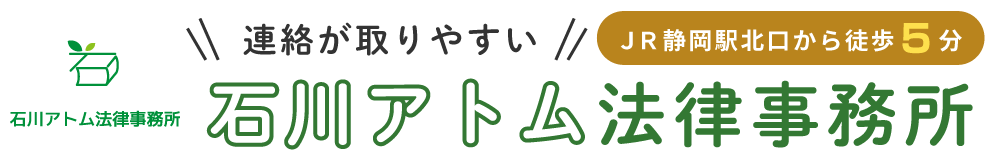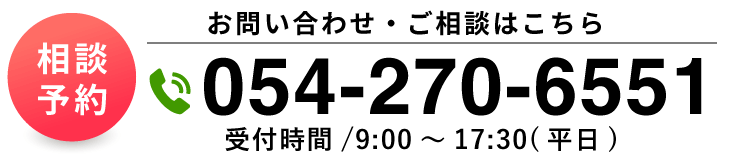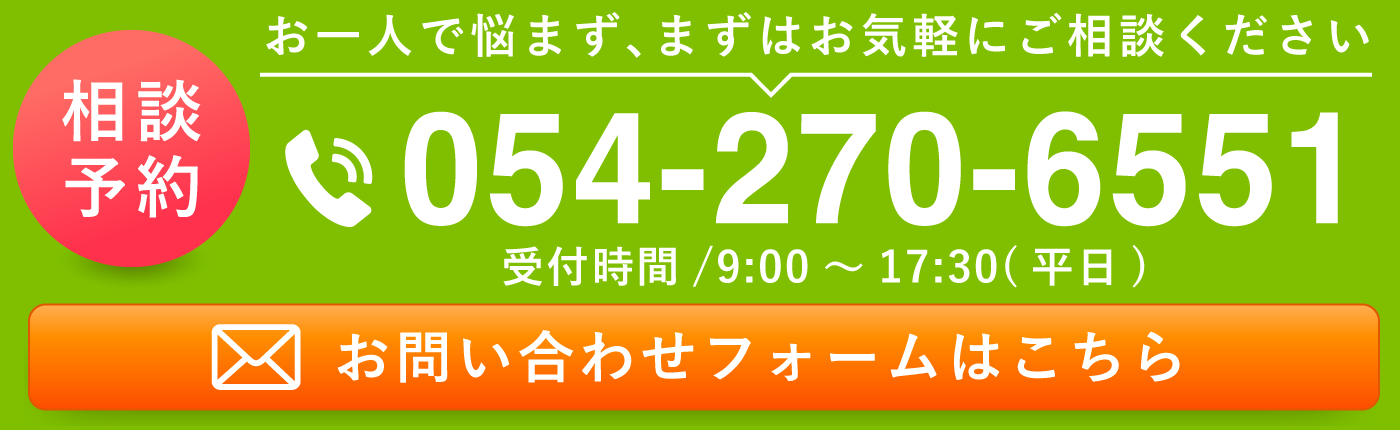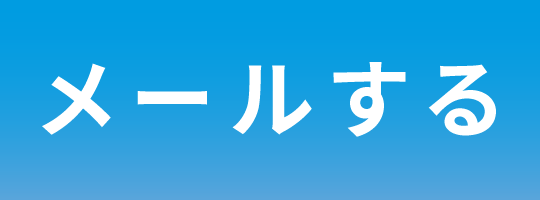このページの目次
「親権」の決め方~親権者の決定において考慮される要素
皆様、こんにちは。静岡市で弁護士をしております石川アトムです。
今回のブログは、「共同親権」に関するブログの第5弾です。
「親権者」がどのような考慮要素によって定められることになるのか、ということを中心にお話しします。
今回もこれまでと同様に、この記事の中では、離婚後の共同親権を指す趣旨で、「共同親権」あるいは「『共同親権』制度」といいます。
改正前民法の世界では、離婚後の親権は、父親の単独親権と母親の単独親権のいずれかしか存在しませんでした。
改正民法が施行されますと、離婚後の親権者のバリエーションは、父母共同(共同親権)、母親単独親権、父親単独親権という3パターンになります。
改正民法下において、親権者が定まる場面は、
協議離婚の際に父母の協議によって定める場合(親権者の指定を求める家事調停を含む)
裁判所が協議に代わる審判をする場合(親権者の指定を求める家事審判)
裁判上の離婚の場合に裁判所が定める場合、という3つの場面が考えられます。
共同親権とするか、父母の単独親権とするかは、「子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮」して決められることになっています(改正民法819条7項)。
離婚後においても、「共同親権」とすることになった場合、一定の例外を除いて、子に対する身上監護、子の財産管理、子の身分行為に関する代理を、父母が共同して行うことになります(一定の例外、すなわち、父母が単独で親権を行使できる場面については、前回までのブログをご参照ください)。
改正民法において、「共同親権」とするか単独親権とするかについて、原則例外は無いとされています。
また、父母のどちらかが反対しているからといって、直ちに共同親権が度外視されるということにもなっていないようです。
「共同親権」とすべきかどうかという判断にあたっては、将来、父母間で、共同での親権行使のための協議や協力を行うことができるかということが検討されますが、協議・協力の程度は、子の養育のために最低限のやり取りができるレベルであれば、その他一切の事情を考慮したうえで「共同親権」を認める余地があると解されています。
なお、「共同親権」であるか否かによって、親子交流(これまで「面会交流」と呼ばれていた離婚後の別居親と子との交流)の方法や充実度について差が生じるという建て付けにはなっていません。
親権者を決める場面での考慮要素~「父母と子との関係」
親権者を決める際の考慮要素として、「父母と子との関係」が挙げられています。
親サイドの事情としては、子の面前で、父母間で口論を繰り返したり、子に対して他方の親の悪口を言ったりするなど、という従前の態度や、養育費を支払うなど親としての責務を果たしているかということなどが考慮されるようです。
子サイドの事情としては、父母に対する子の気持ちや、今後の親権行使に関する子の意向が考慮の対象となり得ると考えられています。
年長の子については、子の意向の重要性は高くなると考えられています。
親権者を決める場面での考慮要素~「父と母との関係」
「共同親権」とすべきか否かの際に考慮される「父と母との関係」は、具体的には、同居時における父母の親権行使の状況、別居後の親権行使の状況、子に対する身上監護のあり方、別居後の他方親と子との交流状況、父母間の連絡状況などに加え、親権者の定めの協議が調わなかった理由などを含む手続の経過についても考慮の対象とされるものと考えられます。
父母の一方が他方に対して、誹謗中傷や人格を否定するような言動を繰り返している場合には、離婚後に親権を共同行使する前提としての父母間の協力義務に違反していると評価される可能性があります。
また、父母の一方が他方に無断で、何ら理由なく子の居所を変更するなどした場合についても、事情によっては父母間の協力義務違反と評価されることがあります。
親子交流について取り決めがされたのに特段の理由無く履行されない場合、養育費に関する協議を理由無く一方的に拒否する場合も、協力義務違反と評価される可能性があります。
これらの協力義務違反は、「共同親権」とするかどうかという場面で、「共同親権」とすることに消極的な事情として考慮される可能性があります。
父母の単独親権とすべきか、共同親権とすべきかは、以上のような考慮要素を総合して決定されますが、改正民法においては、「このような事情がある場合には、絶対に共同親権にはしない」という要素もあります。次回のブログでは、この点についてお話ししたいと思います。
静岡を拠点に活動する弁護士の石川アトムと申します。静岡市に育ち、大学時代に祖母が交通事故に遭ったことをきっかけに、人の人生の大切な一歩を支えたい気持ちが芽生えました。東北大学法学部や京都大学法科大学院で学び、地元で弁護士として働きたい想いを胸に、2022年に独立開業し、石川アトム法律事務所を立ち上げました。事件の進行状況や今後の見通しをこまめに伝えるよう心がけ、ご相談者さまの安心につながればと思っています。趣味は英会話。