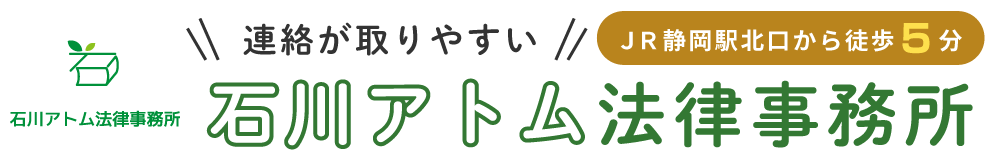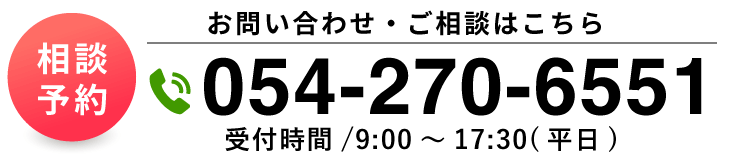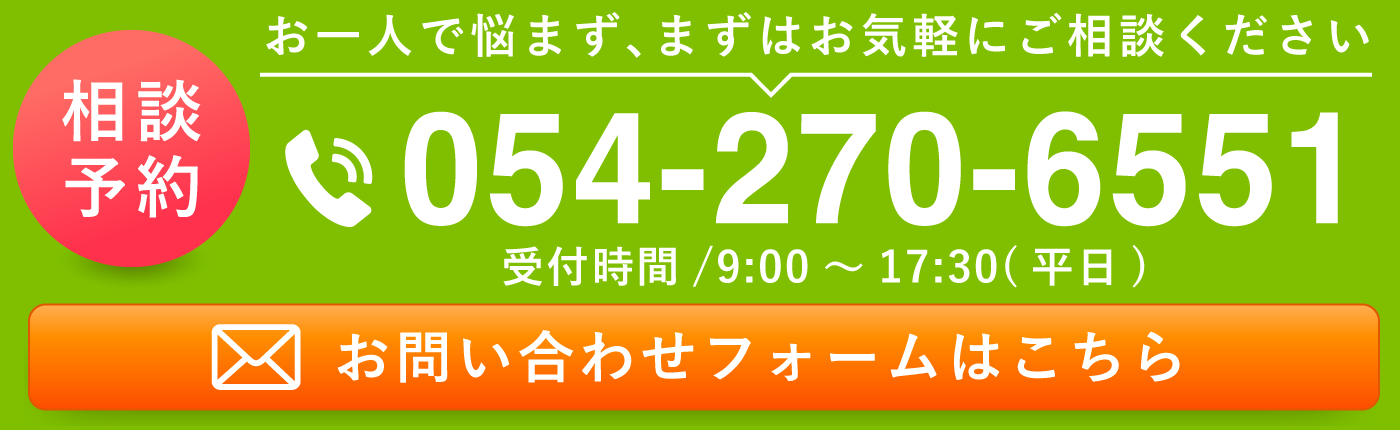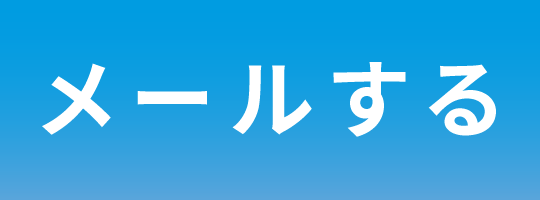このページの目次
共同親権下で父母間に意見の対立があった場合 ~「親権行使者の指定」制度
皆様、こんにちは。弁護士の石川アトムです。
今回も「共同親権」に関するブログで、今回はその第3弾です。
つい先ほど、政府の閣議により、「共同親権」のスタート時期が令和8年4月1日と決定されました。
いよいよ「共同親権」制度が迫ってきたという感じがします。
さて、前回のブログでは、「共同親権」下においても、父母のいずれか一方が単独で「親権」を行使することができる場面について、3つの場合を説明しました。
今回のブログは、「共同親権」下においても、父母のいずれか一方が単独で「親権」を行使することができる4つ目の場面の説明から始めます。
その4つ目の場面は、ある「特定の事項に係る親権の行使」について父母間に協議が調わず、その「特定の事項に係る親権」を父母のいずれか一方に単独で行使させることが「子の利益のため必要がある」と言える場合です。
前回のブログで紹介した父母が単独で親権を行使することができる3つ目の場面、「子の利益のために急迫の事情があるとき」は、父母の意見が対立した際にも使用され得る規定だと思いますが、特定の事項に係る親権行使者が定められる場合というのは、まさに、親権行使について父母の対立があった際に使用されることが想定された規定です。
「特定の事項に係る親権の行使」
この規定は、ある「特定の事項」に関する親権の行使について父母間で協議が調わず、子の利益のためにその「特定の事項」について、父母のいずれか一方が単独で親権を行使する必要があると家庭裁判所が認めたときに、父母の一方による単独親権行使を認める規定です。
この制度は、ある「特定の事項について」という点が大きなポイントです。
特定の、限定された事柄についてのみ親権の単独行使を認める、という制度です。
この規定において想定されている「特定の事項」とは、子の進学先の選択、子の心身に重大な影響を与える医療行為の決定、子の居所の指定や転居、子の財産管理などです。
たとえば、私立中学校へ進学させるか、公立の中学校へ進学させるかについて、父母の意見がまとまらない、といった場面で使用されることが想定されています。
他方で、「親権行使者の指定」制度は、現実に紛争が発生している状態でなければ利用することができません。
近い将来、父母間で子の進学のことで揉めるだろうと思って予め申立てを行う、ということはできないのです。
受験や入学手続にはタイムリミットがありますから、家庭裁判所において実際にどのように調停等を運用していくのか、非常に難しい制度だと思います。
「親権行使者の指定」制度は、先にお話ししたとおり、「特定の事項」について親権を行使する者を決めてもらう制度です。
そうしますと、どの程度の「特定」が必要なのか、ということが実務家(弁護士)としては気になるところです。
この「特定」の程度については、「○○高校との在学契約の締結及びこれに付随する事項」というレベルまで特定する必要はないと考えられています。
親権行使者の指定の申立てをする時点では、子がどの高校に進学するかは確定していないと考えられます。
「○○高校との在学契約の締結」という申立てをしてしますと、仮に申立てが認められたとしても、子が「○○高校」に不合格となってしまった場合、父母のいずれか一方が、当然に、併願していた「××高校」との在学契約を単独で結ぶことができる、ということにはならないためです。
在学契約に関する親権行使者の指定については、「高校との在学契約の締結及び~」というレベルで特定をすれば良いようです。
「親権行使者」の決め方
「特定の事項」について、父母のいずれに単独で親権を行使させるかについては、どのように決められるのでしょうか。
たとえば、高校への進学が問題となっている場面では、①いずれの親が親権を行使する(進学先を決定する)ことが子の利益にかなうのか、及び、②子の意思、意向はどうか、ということが総合的に考慮されて決定されます。
より具体的には、同居期間中における父母の役割分担、子の進学をめぐる父母間や兄弟間でのやり取り、子の年齢、成績、特性等、父母の経済状況、他の兄弟の進学状況、進学先の学校の状況等が考慮されるようです。
進学先の決定に関する親権行使者を決めるにあたって、「どちらの高校がより子どものために良いのか」という観点から検討されるわけではありません。
なお、子の意思、意向はどうか、という点とも関連しますが、子が15歳以上の場合で、裁判所が親権行使者を審判によって決定する場合には、家事事件手続法により、子の陳述を聴かなければならないとされています。
今後のどこかのブログで、子の「居所」に決定に関する事項についても触れたいと思いますが、個人的には、改正民法が施行された後、「親権行使者の指定」制度は爆発的に利用されることになるのではないかと思っています。
静岡を拠点に活動する弁護士の石川アトムと申します。静岡市に育ち、大学時代に祖母が交通事故に遭ったことをきっかけに、人の人生の大切な一歩を支えたい気持ちが芽生えました。東北大学法学部や京都大学法科大学院で学び、地元で弁護士として働きたい想いを胸に、2022年に独立開業し、石川アトム法律事務所を立ち上げました。事件の進行状況や今後の見通しをこまめに伝えるよう心がけ、ご相談者さまの安心につながればと思っています。趣味は英会話。