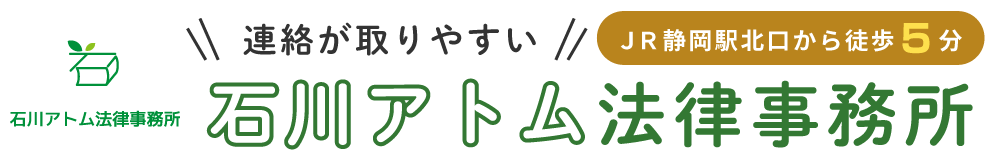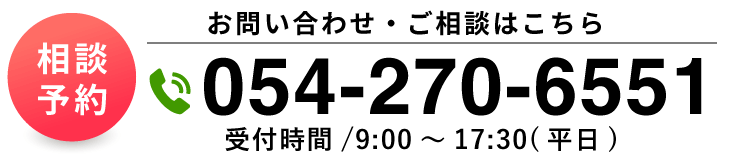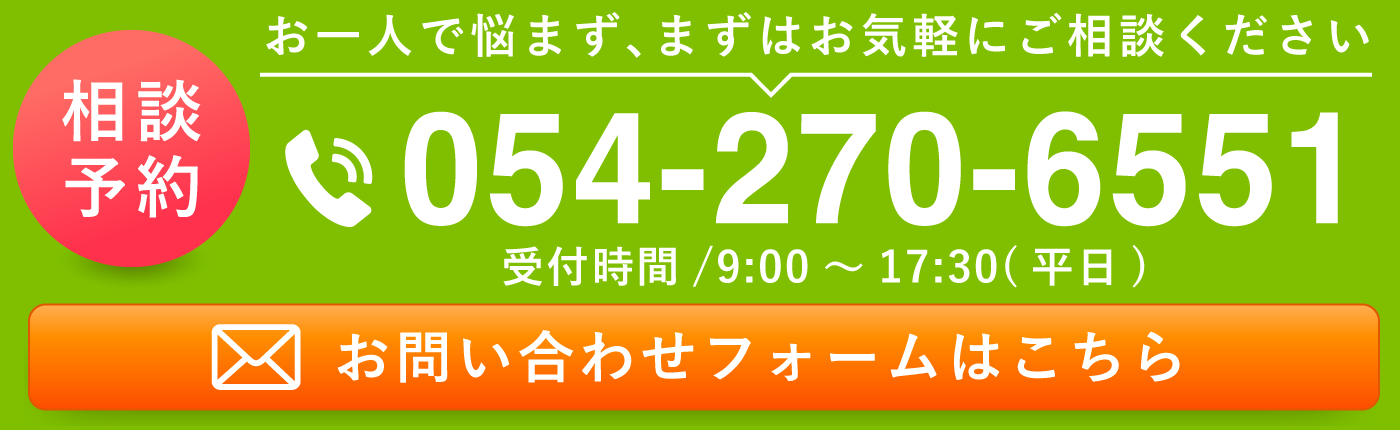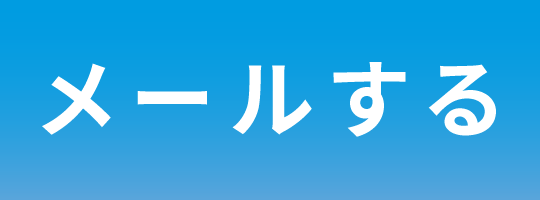このページの目次
日本でも離婚後の「共同親権」制度がスタートします
皆様、こんにちは。弁護士の石川アトムです。
10月に入り、だいぶ秋めいて参りました。
今朝は少し肌寒いくらいの気候です。
さて、来年の5月から、我が国においても離婚後の子どもに対する「共同親権」の制度がスタートします。
私は、普段は会社や個人の自己破産事件を扱うことが多いのですが、静岡県内の弁護士にとって、離婚事件、親権や面会交流に関する事件は、いわば日常的な業務です。
私も離婚事件や親権に関するご相談、ご依頼をよくいただきます。
離婚後の「共同親権」制度がスタートするのは、改正された民法が来年の5月までに施行されるためですが、改正前の民法においても共同親権という制度自体は、婚姻中の夫婦と子との関係において存在していました。
以下では、「離婚後の」という趣旨で「『共同親権』制度」や「共同親権」という用語を用いることとします。
来年5月から「共同親権」制度が始まるということで、静岡県弁護士会においても、「共同親権」制度について既に2回の研修が行われています。
また、来月以降、静岡家庭裁判所の裁判官との3度のパネルディスカッションが開催される予定となっています。
そして、私は、その第1回のパネルディスカッションにおけるパネリストを仰せつかりまして、同役をお受けすることになりました。
しかし、私も、「共同親権」制度について2回の研修を受けただけでして、その程度の知識でパネルディスカッションに臨むことなど恐ろしくてできません。
そこで、「共同親権」に関する書籍などを入手して勉強し、私の知識の定着を兼ねて、ブログで「共同親権」制度についてまとめを作成することとしました。
このような事情から、今回のブログから5回にわたり、今後施行される「共同親権」制度や親権に関連する事項について、シリーズでお話をしたいと思います。
「離婚」の方法には3種類あります
そもそも親権者を決めなければならない場面というのは、子を持つ夫婦が離婚をする場面です。
そこで、まず、日本における「離婚」の方法についてお話をします。
日本では、夫婦が離婚をするための方法は3種類あります。
1つ目は、夫婦が話し合いをして、離婚届を作成し、市役所や区役所などに提出する方法です。
一般に「協議離婚」と呼ばれます。
離婚届には、子の親権者が誰であるのかということを記載する欄があります。
現時点では、未成年の子を持つ夫婦が協議離婚をするためには、夫婦のどちらが子の親権者となるのかを離婚届に記載する必要があります。
2つ目は、夫婦の話し合いの場が裁判所に移り、裁判所の中で話し合いをして、離婚をするという方法です。
裁判所での離婚についての話合いは、正式には「夫婦関係調整調停」と呼ばれますが、より簡単に「離婚調停」とも呼ばれます。
離婚調停を行い、夫婦間で離婚についての合意ができた場合、裁判所が夫婦間での話合いの結果を「調停調書」という書類にまとめてくれます。
当事者が「調停調書」を市役所や区役所に持って行くことにより、戸籍に離婚した事実が反映されます(夫婦間において、別途離婚届を作成する必要はありません)。
このような離婚の方法を「調停離婚」と呼びます。
3つ目は、離婚調停をしても離婚についての話がまとまらない場合、裁判をして離婚をすることになります。
いわゆる「離婚裁判」ですが、日本の法律では、いきなり離婚裁判を起こすということはできません。
離婚裁判を起こすためには、必ず離婚調停を経なければいけないことになっています。
離婚裁判においては、当事者の一方または双方が離婚の原因となる事実を主張し、その事実を証拠によって証明しなければなりません。
離婚の原因となる事実の典型例としては、不貞、不倫が挙げられます。
裁判官が、当事者双方の主張を聴いて、離婚の原因となる事実が認められるかどうかを証拠によって認定し、当該夫婦を離婚させるか、離婚させないかを判決により決定します。
このような離婚の方法を「裁判離婚」と呼びます。
親権者の決定が協議離婚の要件ではなくなります
先ほどもお話ししたように、現在の(改正前の)民法の下では、未成年の子どもがいる夫婦が離婚をするためには、父母のいずれが子の親権者となるかということを離婚時までに必ず決めなければなりませんでした。
逆に言うと、父母のいずれも絶対に親権者になりたいというような場合、協議離婚はできませんでした。
しかし改正民法においては、協議離婚の届けの際に、親権者の定めがされているか、親権者の定めを求める家事審判または家事調停の申立てがされているかのいずれかの条件が満たされていれば、離婚の受付けがされることになりました。
従前、夫婦間で離婚をしたいということについては意見が一致しているものの、夫婦のどちらが子の親権者となるかについて協議がまとまらないために、離婚ができないというケースが相当あったと思いますが、今後は、父母のいずれが親権者となるかという問題を一旦保留にして、離婚した後に親権者を決めるということができるようになりました。
これは、現実問題、かなり大きな改正だと思います。
ただし、離婚調停や離婚裁判においては、改正前と同様に、親権者を決めずに離婚するということはできません。
次回のブログでは、そもそも「親権」とは、どういった権利義務であるのか、という点を中心にお話をしていきたいと思います。
静岡を拠点に活動する弁護士の石川アトムと申します。静岡市に育ち、大学時代に祖母が交通事故に遭ったことをきっかけに、人の人生の大切な一歩を支えたい気持ちが芽生えました。東北大学法学部や京都大学法科大学院で学び、地元で弁護士として働きたい想いを胸に、2022年に独立開業し、石川アトム法律事務所を立ち上げました。事件の進行状況や今後の見通しをこまめに伝えるよう心がけ、ご相談者さまの安心につながればと思っています。趣味は英会話。