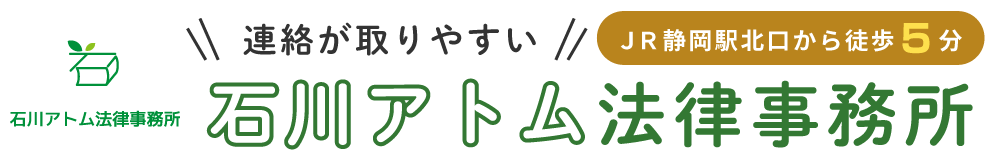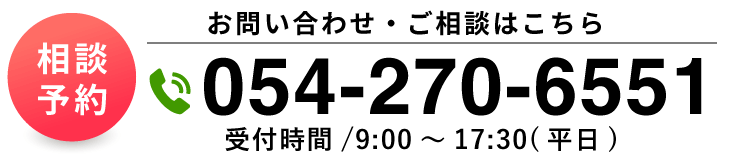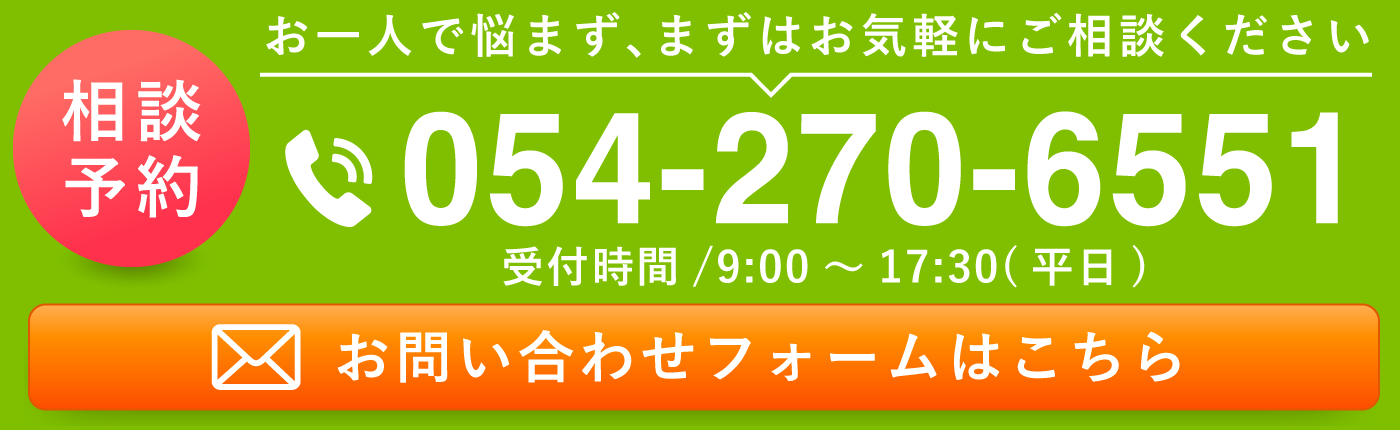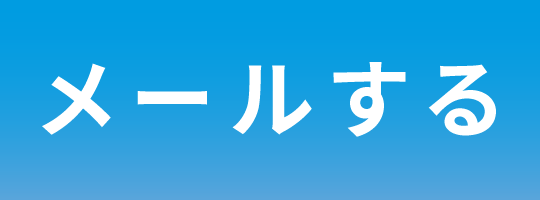このページの目次
離婚後の「共同親権」制度の開始日が令和8年4月1日となりました
皆様、こんにちは。弁護士の石川アトムです。
「共同親権」ブログの第4弾です。
前回のブログで触れましたが、閣議決定により、我が国における離婚後の選択的「共同親権」制度の開始日が令和8年4月1日となりました。
もちろん制度が全く同じというわけではありませんが、既に「共同親権」の制度を有しているアメリカで実施されたある統計によれば、1994年から2010年において、共同親権は25%、母親の単独親権が65%、残りの10%が父親の単独親権という統計結果だったようです。
他方で、日本の「人口動態統計」によると、日本では、2010年の時点で、母親の単独親権は83.3%、父親の単独親権は12.9%、兄弟で親権者が異なるという場合が3.7%だったそうです。
来年4月1日から選択的「共同親権」制度がスタートし、親権の比率がどのように変化していくのか、今後注目していきたいと思います。
親権行使者の指定~子の居所の指定
前回のブログで、「共同」親権下においても、親権の単独行使が可能な場面の一つとして、特定の事項について親権の行使者が指定される場合を紹介しました。
私は、改正民法が施行された後、親権行使者の指定について争われることが最も多い場面は、子の居所の指定になるのではないかと考えています。
と言いますのも、前々回のブログでお話ししたように、「親権」の中には、子どもに関する「身上監護」というものが含まれています。
日常的に子どもと一緒に生活をして、ご飯を食べさせるなどをすることは、親権の中の「身上監護」の一内容です。
改正前民法のもとでは、未成年の子をもつ父母が離婚した場合、父母のいずれか一方だけが子の親権を有するということになっていました。
そのため、改正前民法の世界では、離婚後に親権を持つことになった親が、いわば自動的に、子の住む場所を決めることができていました。
しかし、改正民法が施行された後には、離婚後の父母が「共同親権」を持つケースが出てきます。
先にお話ししたように、親権の内容には、子がどこでどのように暮らすのか、ということを決める権利が含まれています。
そのため、離婚後に「共同親権」となった場合、父母は原則として、子がどこに住むのかを「共同で」決めなければなりません。
共同親権となった場合、どちらか一方の親が当然に子の居所を決めるということはできないのです。
「共同親権」状態の父母において、子の居所について協議がまとまらない場合(父母の双方が、子どもと一緒に暮らしたいと言って譲らない場合など)には、子の居所を指定することについて、親権行使者の指定を求めることが選択肢の一つとなります(ただし、後のブログでお話しするように、どちらか一方が子の居所を定めることをできるようにする手段は、他にも「監護者の指定」や「監護の分掌」という手続もあります)。
このように、「共同親権」と言っても、当然に、父母双方が子と暮らすことができるわけではありません。
今後は、子の「居所」を決める親権行使者の指定が、従前の「親権」争いの一部に取って代わるのではないかと思っています。
子の居所の指定に関する親権行使者指定の概要
子の居所を決める親権者行使者を指定する場面では、父母のいずれが日常的に子を監護することが適切か、ということを子の利益の観点から判断するものとされています。
具体的には、従前の監護状況、現在の監護状況、父母の監護能力、子の年齢、発達状況、父母との関係性、子の意向、兄妹に関する事情について、総合的に評価し、父母のいずれが子の監護をすることが子の最善の利益になるかが判断されます。
子の居所をどこに定めるべきか、ということを直接判断するのではなく、どちらの親に親権を行使してもらうことが子の利益になるのか、という判断の方法が取られます。
この点、前回の子の進学の決定に関する親権行使者の指定に関して述べたことと同様です。
なお、「親権行使者の指定」の制度は、離婚後の「共同親権」下だけではなく、婚姻中の夫婦間においても使用することができます。
今後は、婚姻中の夫婦間においても、子の進学先を決めたり、子どもをその学校から転校させるか否か、退学させるか否かを決めたりする場面で意見がまとまらない場合、親権行使者の指定を求めて家庭裁判所で話し合いを行う(調停を行う)ということが増えてくるかもしれません。
婚姻中の夫婦にとって、この制度が「雨降って地固まる」制度として利用されることになるのか、「覆水盆に返らず」制度となってしまうのか、制度の作用が非常に気になるところです。
静岡市を拠点に活動する弁護士。実務に入り16年目。
中心的な取扱分野は、会社個人を問わず自己破産申立事件。
裁判所の選任により年に数件の破産管財人も担当している。
また、会社の顧問弁護士として会社からの相談を受けることも多い(静岡県外(首都圏)にも複数の顧問先会社がある)。
趣味は旅行、英会話、競馬。