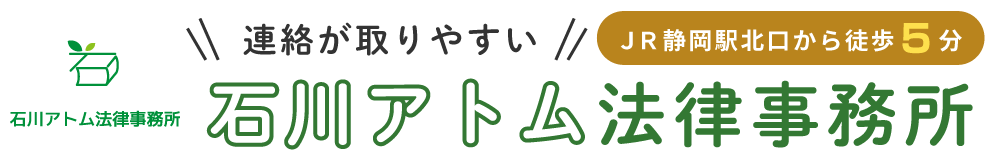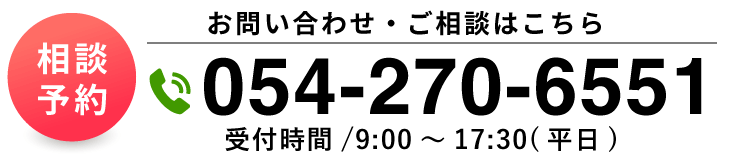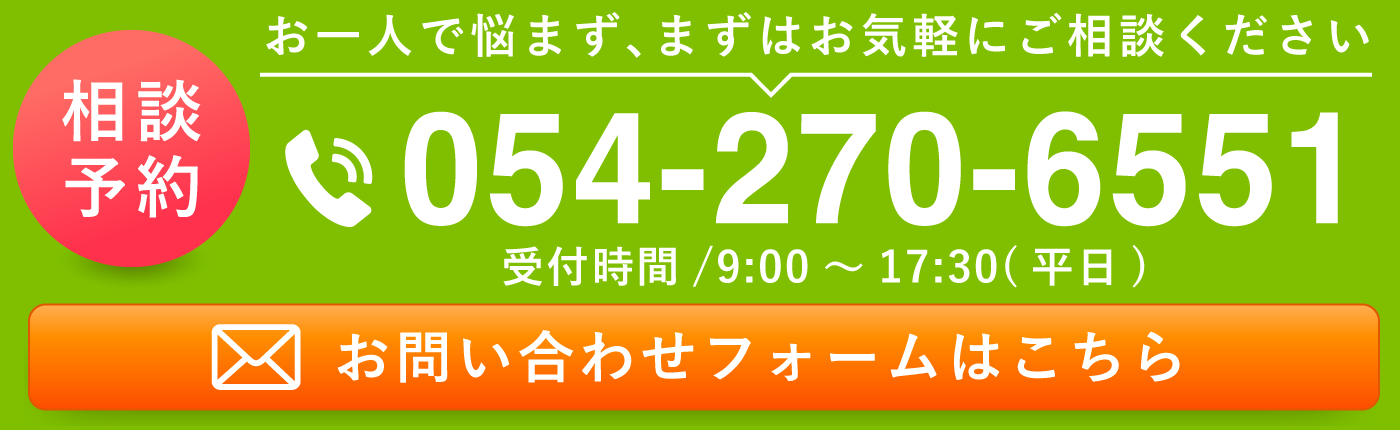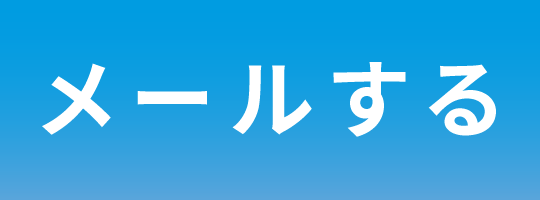このページの目次
「親権」の内容
皆様、こんにちは。静岡で弁護士をしております石川アトムです。
10月も後半に入り、秋めいた空気になってきましたね。
さて、我が国でも、令和7年5月までに離婚後の子どもに対する「共同親権」制度がスタートします。
今回は、「共同親権」に関するブログの第2弾です。
今回も、前回のブログと同様に、「離婚後の」という趣旨で「『共同親権』制度」や「『共同親権』」という用語を用います。
「共同親権」シリーズのブログをお送りしていますが、そもそも「親権」の内容とは何でしょうか。
「親権」というと、子どもと一緒に生活をして、子どもの面倒を看て、教育をして、というイメージがあると思います。
そういった行為をする親の権利義務も「親権」の一部です(「身上監護」といいます)。
しかし、「親権」には、子に対する身上監護だけではなく、子の財産を管理する権利義務(「財産管理」)も含まれます。
このほか、「親権」には、子の身分行為を代理することも含まれます。
身分行為としては、子の氏の変更などがあります。
改正民法では、このような「親権」について、親の権利という性質だけではなく、親の子に対する義務としての側面もあるということが明記されています。
「共同親権」でも「親権」の単独行使が可能である場合
「親権」は、夫婦が婚姻中であれば、共同して行うことになります。
また、来年の5月以降は、夫婦が離婚した後も「共同親権」ということになれば、父母が共同して「親権」を行使することになります。
しかし、常に、父母が親権を共同で行使しなければならないとすると、子の利益を害するような場面も出てきます。
そこで、改正民法上、以下の場合には、「共同親権」の状態にあっても、父母のどちらか一方が単独で「親権」を行使することができると定められました。
①父母の一方が親権を行うことができないとき
②監護教育に関する日常の行為をするとき
③子の利益のために急迫の事情があるとき
④特定の事項について家庭裁判所の許可により親権行使者が定められた場合
以上の4つのうち、②から④は改正民法によって新設された規定です。
今後特にポイントになってきそうな規定は、③と④だと思います。
①から④を順に見ていきましょう。
まず、①「父母の一方が親権を行うことができないとき」です。
これは、父母のいずれか一方が長期の旅行に行ってしまった場合、行方不明になってしまった場合、受刑者になってしまった場合、成年後見の開始を受けた場合、親権喪失の宣告がされた場合などが当てはまります。
「監護教育に関する日常の行為をするとき」
次に、②「監護教育に関する日常の行為をするとき」です。
「監護教育に関する日常の行為」については、単独での親権行使が認められます。
ただし、あくまでも、親権のうちの日常的な「身上監護」に関するものについての親権行使です。
後に述べる別の例外ケースに該当しない限り、子の財産管理や身分行為の代理をするためには、共同での親権行使が必要です。
どのような行為が「監護教育に関する日常の行為をするとき」に当たるのか、ということについては、法務省民事局のパンフレットに言及があります。
具体的には以下のような例が挙げられています。
・食事や服装の決定
・期間の観光目的での旅行
・心身に重大な影響を与えない医療行為の決定
・通常のワクチン接種
・習い事
・高校生の放課後のアルバイトの許可
他方で、「日常の行為」に該当しない例としては、以下のような事由が挙げられています。
・こどもの転居
・進路に影響する進学先の決定(高校に進学せず就職するなどの判断を含む)
・私立小中学校への入学、高校への進学・退学など
・心身に重大な影響を与える医療行為の決定
・財産の管理(預金口座の開設など)
「子の利益のために急迫の事情があるとき」
共同親権下において、単独での親権行使が可能な場面の3つ目は、「子の利益のために急迫の事情があるとき」です。
こちらは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時の親権行使をすることができず、その結果として子の利益を害するおそれがあるようなケースを指すと言われています。
法制審議会では、入学試験の合格発表後に行われる入学手続、緊急で医療行為を受ける必要がある場合の診療契約、DVや虐待から逃れる必要がある場合などが検討されたようです。
他方で、手術日まで2、3か月程度の余裕があるときには直ちに「急迫の事情があるとき」には当たらないとの法務大臣の答弁もあったようです。
どのような場合が「子の利益のために急迫の事情があるとき」に当たると判断されるのかは、個別具体的なケースごとに異なると考えられ、改正法施行後の事例の集積を待ちたいと思います。
④の特定の事項について家庭裁判所の許可により親権行使者が定められた場合については、次回のブログでご説明いたします。
静岡市を拠点に活動する弁護士。実務に入り16年目。
中心的な取扱分野は、会社個人を問わず自己破産申立事件。
裁判所の選任により年に数件の破産管財人も担当している。
また、会社の顧問弁護士として会社からの相談を受けることも多い(静岡県外(首都圏)にも複数の顧問先会社がある)。
趣味は旅行、英会話、競馬。