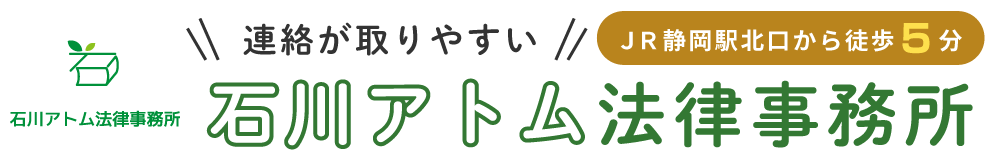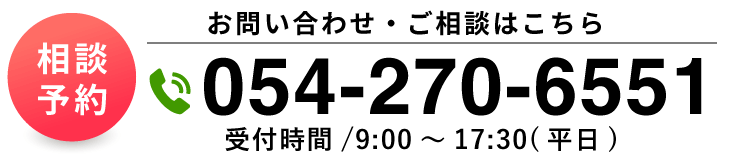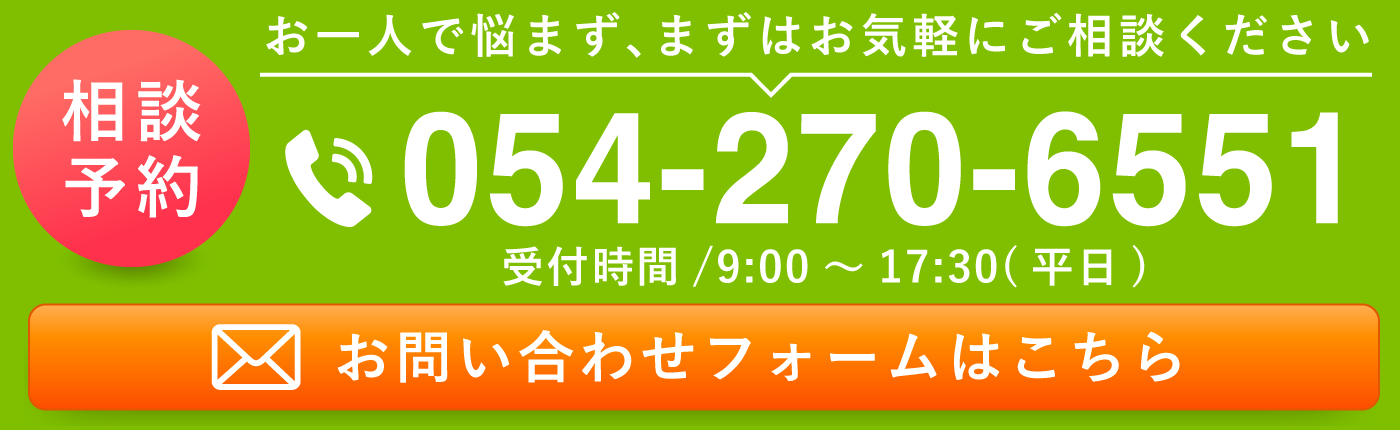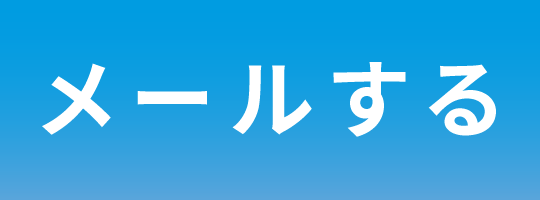このページの目次
弁護士の仕事を裁判所から見る修習
皆さん、こんにちは。弁護士の石川です。
昨秋連載(?)していた司法修習の思い出ブログですが、途中で止まってしまっていたので、最後まで書き上げたいと思います。
最後にご紹介したのは、民事裁判修習に関するお話でした。
さて、私にとって、民事裁判修習は、刑事裁判、弁護修習に続く、3つ目の実務修習でした。
弁護修習では、お二人の指導担当弁護士の先生に付いて、色々な事件を見せていただきました。
現在の私と同じく、お二人の指導担当弁護士も、業務の大半(9割以上)は、民事事件でした
(民事事件と刑事事件の違いについては、こちらのブログをご参照ください)。
弁護士の仕事の多くが裁判所で行われるものかというと、決してそうではありません。
裁判所を使わずに解決できる事件もそれなりに多いのです。
しかし、どうしても裁判所外の話合いで解決ができなれければ、最終的には、裁判手続を利用して決着をつけるしかありません。
指導担当弁護士の言葉を借りれば、「裁判所を利用させていただく。」ということになります。
本来、裁判修習は、裁判官のお仕事を勉強させていただくものだとは思うのですが、弁護士志望であった私にとって、民事裁判修習は、弁護士の仕事を裁判所の視点から見ることができる修習であり、大変勉強になりました。
特に、裁判手続中に行われる和解勧試に同席させていただくことが何回かあり、裁判官が、どのようなことを双方当事者に言って、互譲を引き出し、和解を成立させようとするのか、その過程を見ることができ、参考になりました。
裁判官へのリクルート
先ほど、当時の私は弁護士志望であったというお話をしましたが、厳密には、民事裁判修習に入った時点で、弁護士8.5、裁判官1.5くらいの割合で弁護士志望でした。
司法試験に合格した人は、裁判官、検察官、弁護士のどれかになることができます(うちの妻にこの話をしたら、イーブイだねと言われました。でも、今って、イーブイの進化は3種類じゃないんですね!!)。
司法修習が始まる前までは、裁判官になるということは全く考えていませんでした。
しかし、1つ目の実務修習である刑事裁判修習の間に、事実認定の面白さに目覚め、少しだけ裁判官志望という気持ちが芽生えてきました。
ただし、依然として弁護士志望の気持ちの方が圧倒的に強く、司法修習後は弁護士になるということはほとんど決めていたのですが、民事裁判修習を見てから、最終的に、弁護士になるか、裁判官になるかを決めようと考えていました。
しかし結局は、調理済みの2つの料理について、どちらが美味しいかを判断するよりも、相手方よりも美味い料理を作ったと認めさせる方が面白そうだ、という気持ちが一層強くなってしまい、民事裁判の終了時点で、裁判官ではなく、弁護士になることを決めました。
裁判教官からは、サシでお酒を酌み交わす機会をいただき、「君には大きな幹のように育ってもらいたい。」とお誘いいただいたり、静岡修習でありながら、東京地方裁判所の医療部の裁判官の皆様と懇談をさせていただく機会をいただいたりするなど、裁判官への勧誘をいただいておりました。
また、「裁判官になったら、留学できるよ。」というお話もあったのですが、高所恐怖症もあり、当時の私はあまり飛行機が好きではなかったのです。
海外旅行が大好きになったのは、修習から5、6年ほど後の事務所旅行(台湾)からでした。
しかし、仮に、その5、6年後に、勧誘を受けていたとしても、裁判官になるということはなかったと思います。
私の中で、司法試験を目指そうと思った動機は、静岡で弁護士になるためであり、元々自分が、ある組織の一員として働くということに向いていない人間だろうと思っていたためです。
そして、民事裁判修習を経た結果、実際の仕事の中身としても、弁護士の方が面白そうだと確信してしまったのです。
現在、弁護士になって14年ほどになりますが、この選択は正しかったと思っています。
結婚生活を漢字一文字で表すと・・・忍耐の「忍」!!
民事裁判修習中も裁判官との飲み会がありました。
当時の裁判所は、まだまだその辺りの規制が緩かったと思うのですが(多分今はダメだと思いますが)、裁判官との飲み会は、裁判所の裁判官室で行われました。
その席上、非常に記憶に残っているトピックがあります。
裁判官は、基本的に3年で転勤となり、全国規模で異動があります。
おそらく、単身赴任をして地方に行くか、東京から新幹線で通うかという話の延長線上だったのではないかと思うのですが、男性裁判官の一人が、結婚生活を漢字一文字で例えると、みたいな話を始めたのです。
当時、静岡地方裁判所の民事部に、男性裁判官は5、6人いたと思うのですが、皆さん異口同音に、「忍耐の『忍』!!」とおっしゃっていました。
世間的には地位の高い裁判官も、家庭では色々大変なんだろうと、25歳になったばかりの若輩にとって、非常に印象的な会話でした。