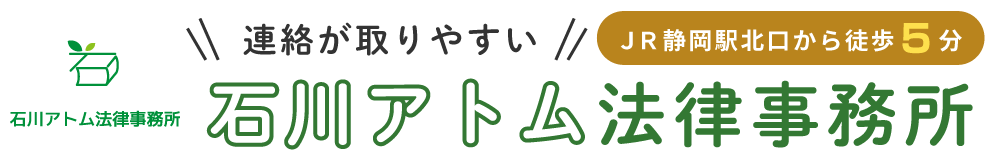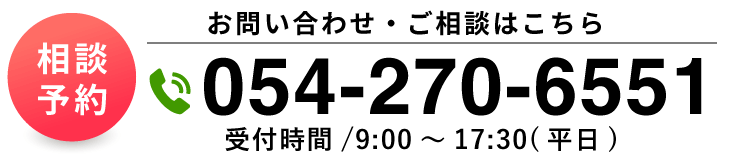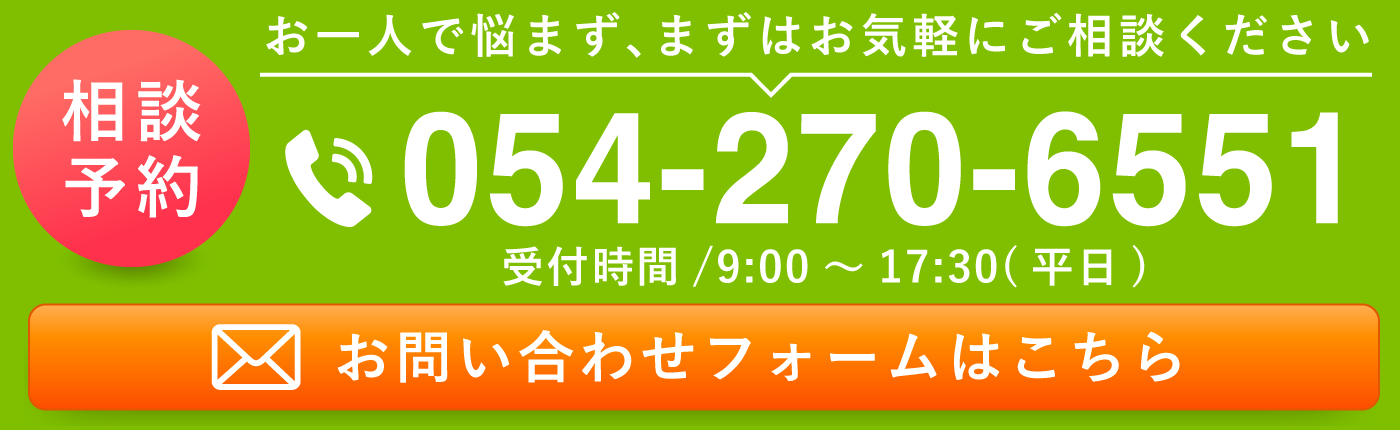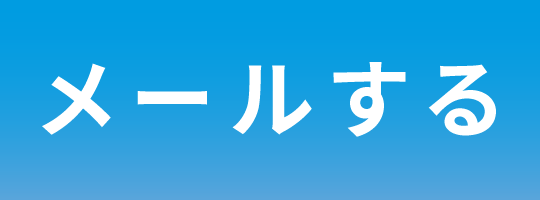このページの目次
1 不当解雇の代償
(1)解雇を「簡単に」考えてはいけません
経営者の中には、解雇というものを非常に簡単に考えられている方がいます。
ここでいう「簡単に」とは、2つの意味があります。
1つ目は、解雇を行うための要件を「簡単に」考えているということです。
経営者が「クビだ」と言えば解雇できるとまでは言わなくても、ちょっとした従業員のミスや態度をもって解雇が可能である、30日分の給与(解雇予告手当)さえ支払えば解雇が可能である、というようにお考えの経営者の方は少なくないと思われます。
しかし、後に述べますが、これは大変な誤解です。
2つ目は、解雇の効果を「簡単に」考えているということです。
解雇をすれば従業員との関係がすべて清算され、何も問題は残らないというものではありません。
解雇をした場合、従業員本人やその家族に与える影響が大きいことはもちろんですが、解雇をした企業においても、同解雇が結果として「不当解雇」に当たる場合のみならず、「不当解雇」にあたるおそれがある場合にも多大な影響が生じます。
まずは、解雇が「不当解雇」と判断された場合の効果についてご説明いたします。
(2)「不当解雇」と判断された場合の効果
従業員を解雇した場合、通常、企業は、解雇後、当該従業員が企業の事務所や営業所、あるいは、工場内において働くことを拒否します。
つまり、企業は、従業員から提供される労働を受け取らないという態度を示すことになります。
解雇が無効とされた場合、従業員が企業に対して労働を提供できなかったのは、企業が不当に従業員を解雇して従業員からの労働を受け取らなかったからだ、ということになり、企業は、従業員が働くことができなかった期間に対応する給与相当額を支払わなければならなくなります。
解雇が無効であることを確認する裁判(正確には、従業員の地位にあることの確認を求める裁判)が起こされた場合、裁判が終結するまでには少なくとも1年程度の時間がかかります。
一審判決に不服があって控訴されれば、あるいは、企業側が控訴せざるを得なければ、訴訟が提起されてから控訴審の結論が出るまでに2年以上の時間を要することもあります。
仮に解雇から解雇無効判決の確定まで2年かかったとすると、企業は、従業員から労働の提供を受けていないにもかかわらず(企業が労働の受け取りを拒否しているので当然ですが)、従業員に対して2年分の給与を支払わなければならない、ということになるのです。
そのため、解雇が無効であることを確認する裁判の中では、企業に対して、解雇の無効確認とともに、従業員が解雇されてから復職できるまでの期間に対応する賃金請求が行われることが通常です。
また、解雇の仕方によっては、解雇の無効確認及び給与相当額の支払い請求(賃金請求)に加えて、解雇を行ったこと自体によって精神的苦痛が発生したとして、慰謝料の支払いを求める請求が加わってくることがあります。
さらに、裁判の中で、解雇が無効であるということになると、理屈上従業員は復職することになります。
しかし、実際には、解雇無効の裁判によって従業員が会社に復帰するというケースよりも、従業員には会社を退職してもらい、その代わり、企業が、本来の退職金とは別に、ある程度の解決金を上乗せして支払うというケースの方が多いのではないかと思います。
解雇が不当解雇であったと判断された場合、企業は、①裁判が終了するまでの期間に対応する給与を支払い、②解雇の仕方によっては慰謝料を支払い、③従業員が退職するにあたって退職金とは別に解決金を支払う可能性がある、という大きな経済的負担を負うことになります。
(3)解雇の要件
「30日分の給与(解雇予告手当)さえ支払えば解雇できるのではないのですか?」というご質問がよくあります。
しかし、このようなお考えは、とんでもない誤解だと言わざるを得ません。
解雇予告手当を支払うことは、解雇の手続的な要件(取るべき手続としての形式的な要件)であり、解雇の実体的な要件(当該従業員を解雇できる理由があるのか、という中身としての要件)が満たされていない場合には、いくら解雇予告手当を支払っていたとしても、解雇は無効です。
普通解雇の場合ですが、企業が従業員を解雇できるのは、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められる場合です。
このような要件を満たすことは、一般的に言って極めてハードルが高いです。
ちょっとやそっとのことでは、従業員を解雇することなど到底できないということです。
また、従業員が病気や怪我で業務ができなくなったという場合には、その病気や怪我が業務上生じたものであるのか、私生活上生じたものであるのか、当該企業において私傷病の休暇制度はあるのか、怪我や病気による業務への影響はどの程度かなどを考慮して、適切に対応をしていく必要があります。
2 解雇手続を取る前の弁護士への相談が重要です
(1)解雇してからでは手遅れです
当該解雇が不当解雇だということになれば、企業に対しては、先ほどお話ししたような大きな影響が生じます。
そのため、解雇は極めて慎重に行わなければなりませんし、解雇をするかどうかについては、再考を要する場合の方が圧倒的に多いのではないかと思います。
一旦解雇をしてしまうと、手遅れとなってしまうケースがほとんどだと思います。
従業員を解雇することが頭をよぎったら、まず弁護士に相談し、当該従業員を解雇することが法的に可能かどうかを相談するべきです。
(2)解雇無効訴訟を避けるために
もちろんケースバイケースですが、従業員に職務への適格性の欠如が見られたり、職務怠慢と思われる態度があったり、企業秩序を乱すような行為があったとしても、多くの場合、直ちに従業員を解雇することはできません(解雇したとしても、当該解雇は無効と判断されるおそれが高いです)。
このような場合、企業側と従業員とで話し合いをし、場合によっては、合意退職という形を取ることも考えられます。
合意退職となれば、その合意が企業側による不当な退職勧奨等に基づくものでなければ、従業員による退職は有効となり、紛争リスクは大きく軽減されます。
(3)裁判になること自体が企業にとっての負担です
このページの最初の項において、「『不当解雇』にあたる恐れがある場合にも」企業側に多大な影響が生じると記載しました。
解雇の無効を確認する訴訟が提起され、最終的に解雇が有効であったと判断される場合でも、従業員から解雇無効の裁判が起こされた場合、企業はこれに対応せざるを得ません。
裁判には少なくとも1年程度の時間がかかります。
その間、どのような事情で当該従業員を解雇したのか、当該従業員を解雇した理由となる事実はどのような証拠により裏付けが取れるのか、ということについて、企業は何度も打合せをする必要があります。
そのため、裁判が起こされると、先に述べたような経済的な負担やリスクがあるだけではなく、訴訟対応のために、経営者や人事担当者の通常業務が圧迫されるおそれがあります。
円滑な企業活動を継続していくためにも、可能な限り訴訟が提起されることは避けるべきです。
そのためには、紛争の種となり得る「『不当解雇』にあたるおそれがある」解雇は行うべきではありません。
従業員への解雇が頭をよぎったら、まずは弁護士に相談することをおすすめします。